第2章 西洋の楽譜の歴史
1.グレゴリオ聖歌とネウマ譜
古代ギリシアの記譜法は、ヘレニズム、ローマを通じ、各地方で使用された。《オクシリンコスの賛歌》は、270年ごろ書かれた現存する最古のキリスト教音楽と考えられているが、楽譜は、ギリシアの声楽譜によっており、その発見場所は、エジプトである。古代末期の記譜法の資料はあまりにも少なく、未だ決定的な学説はでていないのが現状だ。古代末期からキリスト教の波及とともに、各地の教会が、独自の聖歌を持つにいたるのだが、これらの聖歌が、ほとんど口授伝承により伝えられたため、楽譜資料は乏しい。しかし、古代ギリシアの遺産が、当時、そして、中世の記譜法にほとんど受け継がれていなかったことは明らかである。娯楽としてのギリシアの音楽表現と違い、聖歌は、キリスト教の聴覚的サクラメントだったのかもしれない。また、より、今日的に考えれば、それは、むしろ、受け継がれてはいけないのである。なぜなら、古代ギリシアと中世では音楽様式も音楽観もまったく異なるからである。中世は、中世の音楽観に見合った記譜法を創出していく必要があるのだ。
中世初期の楽譜は、そのほとんどが聖歌を示すものであり、それが、典礼において必ず歌われるものである以上、そのリズムや旋律は楽譜の手を借りなくとも、歌い手にとっては周知のものであった。ただ、記憶の一助として、記述した「記述的」楽譜という側面が強いだろう。
さて、先に述べたように、初期のキリスト教においては、ローマの他にも、今でいう、アンプロジオ聖歌、ガリア聖歌、モザラベ聖歌 など各地にそれぞれの聖歌が存在した[注15]。聖歌というのは、修道院などで行われる聖務において、聖書の朗読とともに、歌われるものをさし、それは、典礼や礼拝の様式に密接に関係している。つまり、聖歌が統一されていないということは、信仰形態さえ律されていないとも換言できるのではあるまいか。そこで、その統一に尽力を果たしたのが、教皇グレゴリウス1世 Gregorius Ą(c.540-604)であったされている。キリスト教の総本山であるローマ教皇が定めた聖歌、カントゥス・ロマヌス(ローマ聖歌)を俗に《グレゴリウス聖歌 Cantus Gregorianus》と呼ぶようになったのは、まさに、そのことに由来している[注16]。
そのグレゴリオ聖歌の記譜法として一般に知られるのが、先にも紹介したネウマ譜である。ネウマとは、「合図」「身振り」などを現わすギリシア語の(υενμα)からきている。ネウマは、ギリシアの文字譜のようにやはり、歌詞の上に施され、その形状で、音の移動の度合を現わす独自の記号体系である。その記号は、話す時の手ぶりを模式化した古代ギリシアの文法アクセント記号からきているという説が有力であるが、この記譜法が、いつ、どこで、どのような人達によって発明されたのかということについては、まったく分かっていない。現在知られている最古のネウマ譜は9世紀のものであり、この時期において、聖歌を記譜するという習慣が生まれたとするのが、定説となっているが、それ以前に、楽譜がなかったわけではないだろう。グレゴリウス1世の時代にも、なんらかの、聖歌のメロディを記述するシステムがあったのかもしれない。ローマには、グレゴリウス1世の時代より以前に、後にスコラ・カントルム(「歌の学校」)と呼ばれるようになる聖歌隊の養成所があったことが確実視されている。
時代の後先は別にしても、このような学問組織や、聖職者たちが、聖歌をメロディとして識別し、定まった形式を定着させるために、記譜法のような体系を必要としたことは疑いがない。それはリートを伴奏に歌う古代ギリシアの記譜法ではなく、聖歌の記述のために生まれた記譜体系なのである。
747年のグラスゴウの宗教会議において、聖歌合唱は、ローマ教会から「記録されて」「伝えられたもの」に従うということが布告された。このことからも、初期の楽譜が、求められた役割は、端的にこの二つ、「記録」と「伝播」に集約するといえるだろう。これは「記述的」楽譜にあたるものが、制作され、それを読譜する法則も完成していたことを示しているのではないだろうか。音楽を可視化する目的は、こうして整えられた。そして、9世紀になり、多くの聖歌が記譜され、写本として全国に拡大していくようになる。現存する最古のネウマも、スイスのザンクト・ガレン修道院の図書館に蔵されていたものである。そして、ネウマは、その波及の過程で、様々な形状の変化をうけ、基本的な、ザンクト・ガレン型の他にも、メッツ型、ベネヴェント型、アクィタニア型など、約15種類に及ぶ地方型に派生した。(譜例2-1)
この初期のネウマは、その様式から一般にカイロノミー的記譜法 cheironomic notation と呼ばれている。あるいは、ネウマ自体をカイロノミック・ニュームcheironomic neuma [注17] と呼ぶ。ネウマの由来をギリシアのアクセント記号とする説に基づくならば、それは、合唱長の指揮と関係したと考えうる。つまり、高アクセント acutus(/)が、上昇を示すヴィルガ virga になり、低アクセント gravis(\)が、下降を示すプンクトゥム punctum になったというものだ。おそらく、現代の指揮のようにリズムを律するものではなく、音程の上下をネウマと同様に、文字通り指示したのだろう。カイロノミック(「手動」の意)という言葉もこれに由来する。カイロノミック・ニュームは、ネウマが、ほとんど一直線上にならんでいるもので、実際の音の高さは明確ではない。つまり、この楽譜から得られる情報は、その音が前の音よりどれぐらい上か、あるいは下かということだけである。これは相対的な音程しか表示できない。どちらかというと、歌唱の旋律のニュアンスを指定しているように感じられる。
11世紀末ごろからベネヴェンドやアクィタニアなどの地方に、空間的な隠喩を取り入れたネウマが見られるようになる。すなわち、空間の上の方は高い音、下の方は低い音という概念である[注18]。これによって、ネウマの位置は音によって上下にずれ、視覚的に旋律の流れが理解可能になった。これを、ケイロノミー的記譜法に対して、音程的記譜法 diastematic notation と呼び、そのネウマをディアステマティック・ニューム diastematic neuma という。しかし、それでも、その相対的性格は、変わらず、したがって、途中で一度でもその音程差を読み違えれば、その後、最後まで、間違えたままになり、理論上、それに気がつくことはない。
音高を示す文字を添える方法などが試されるなかで、水平の線が1、2本引かれ、上下関係が一層分かりやすくなった。この譜線は、最初の頃は、絶対的な音程を表わすものではなかった。おそらく、我々が、白紙に文字列を書くとき、それが斜めにずれていかないように引く罫線のようなものとして、写字生などが発案したのがきっかけだったのだろう。やがて、その線に色がつけられたり、CやFといった近代でいう音部記号がつけられるようになり、一定の音高を明示できるようになった[注19] 。これらは、譜線付きネウマ staff neuma と呼ばれ、この譜線は、明らかに、近代五線譜法に通じる第一歩となった。最終的には、13世紀ごろに、3度の音程[注20]ごとに、4本の線を引き、四角ネウマで音高を書き込むシステムが確立された(譜例2-2) 。これは、現在のグレゴリオ聖歌の記譜法でもある[注21] 。
。これは、現在のグレゴリオ聖歌の記譜法でもある[注21] 。
このネウマが基準線を挟んで上下に蛇行する姿で、メロディを線描的に可視化することによって、その旋律は、たとえ、歌ってみなくても、容易に理解できるようになった。相対的だった空間の隠喩的使用の概念は、譜線を得ることによって、絶対的音高の記述に至った。この点は、音楽の可視化と記譜法の点から高く評価されるべき一つの完成型と言えるだろう。
しかし、リズムの表示は、なされなかった。現在では、ソレーム派による解釈として、全ての音を同じ長さで歌う方法がとられているが、この解釈を正統化するいかなる証拠もない。むしろ、聖歌の性質を考えた時、そこには、強調すべき様々な、名前や言葉が登場するはずである。それらが、他の、つまり一般的な言葉と同じように、平等に扱われていたとは考えにくい。聖歌が、まったく個性的な律動感をもって歌われていなかったとは誰も断言できないのである。
2.オルガヌム
記譜法が存在しなくても、音楽はある。多くの文化圏が、素晴しい音楽を持つが、それを記録する記譜法は存在しないこともある。その時、そのように楽譜なしで奏でられる音楽を、現在の我々は「即興 improvisation」と呼ぶ。音楽が、楽譜の存在によって「即興」ではなくなる時、そこに近代的な「作曲 composition」という概念が生まれる[注22] 。「規範的」楽譜というものが書かれるようになるのである。
西洋も、この時代、音楽のほとんどは彼等の言う「即興」であった。ポリフォニーの元祖とも言えるオルガヌムでさえ、即興で歌われていた。ポリフォニーとは、簡単に言えば、二つ以上の声部からなる音楽を指す。つまり、オルガヌムは、二人以上の歌手によって歌われていた(合唱されていた)にもかかわらず、即興が可能だったのである。それは、ある理論の存在によって可能になっていた。作者不詳の『音楽提要 Musica Enchiriabis 』と『学問提要 Scholia Enchiriadlis 』という理論書がそれである。この二冊の書物は、前者に後者が続く形で書かれている。『音楽提要』では、古代ギリシアのテトラコルド論(一種の和声論)を音楽演奏に応用する方法が書かれており、その中に、タジア譜[注23]と呼ばれる特殊な記譜法が現われる。これは、オルガヌムの歌い方を説明したものであり、オルガヌムが即興で歌われていた以上、それはすなわち作り方を説明したものだとも言える。
さて、初期のオルガヌムでは、主旋律、つまり聖歌からとられた基本となる旋律をヴォクス・プリンチパリス vox principalis[注24]と呼び、それに付け加えられる対旋律を、ヴォクス・オルガナリス vox organalisと呼んだ。『音楽提要』や『学問提要』によると、初期のオルガヌムは、ヴォクス・プリンチパリスの完全5度下にヴォクス・オルガナリスを加えることからはじまる。標準的な4声のオルガヌムは、ヴォクス・プリンチパリスの完全4度上と、完全5度および完全8度下に平行に動きを保つ、三つのヴォクス・オルガナリスからなるが、これは、二声のオルガヌムの、ヴォクス・プリンチパリスを完全8度下に、ヴォクス・オルガナリスを完全8度上に重ねることによって得られる。これらの、音程は、ピュタゴラス派のいう協和音程にほかならない。このようなオルガヌムを平行オルガヌムと呼ぶが、平行に動く声部には、理論上、これらの協和音程だけにおさまらない箇所がでてくる。例えば、H音とF音が重なる時、そこには、増4度音程があらわれる。この音程は、「音楽の悪魔」 として、中世では禁じられていた[注25]。理論書としては、時としてあらわれるこの禁忌の音程を避けるため、完全に平行ではない音の動きを許容し、そこに自由オルガヌムがうまれる要素ができた。
11世紀前半に活躍したグイード・ダレッツォ Guido D'Arezzo (990-?) の著作『ミクロログス Micrologus 』や、作者不明の『オルガヌム創作法 Ad Organum faciendum 』などの書物において、長2度(トヌス)や長3度(ディトヌス)などの使用が推奨され、自由オルガヌムの発展に拍車がかかる。
オルガヌムは多くの理論書で解説され、実例が楽譜として掲載された。音楽がほとんど即興だった時代に、理論書が、それを解析するという形で、記譜を進めていた。理論が単純な平行オルガヌムの場合は、記譜によらなくとも説明は安易にすむが、自由オルガヌムのように複雑化したオルガヌムは、記譜によって説明したり、実例をあげることが要求される。
現存する最古のオルガヌム曲集は、984年から1050年にイギリスで作成された174曲のオルガヌムを集めた《ウィンチェスターのトロープス集 Winchester Troper 》である。トロープスとは、既成の聖歌の旋律に新たな歌詞をつけたものを指すが、このイングランド特有の付線なしネウマで書かれた手稿本は、旋律の相対的上下行以外を読みとることができない。正確な音程で再現できないままである。続いて、アキテーヌ方式のネウマで書かれた手写譜がサン・マルシャル修道院とサンチャゴ・デ・コンポステラ大聖堂に保管されていた。後者は、《カリクスティヌス手写本 Calixtinus Codex 》と呼ばれているが、この教皇カリクスティヌス˘世が編集したというのは真実ではない。これらの写本の中の初期のものは、1100年頃に筆写されている。このアキテーヌ方式のネウマは、音の高さはほぼ正確に読みとれるが、やはり、リズムは記述されず、グレゴリオ聖歌同様、現在では、すべての音を同じ音価で歌う方法がとられている。
つまり、いままで、口授されてきた聖歌を、記録するために使われていた記譜法が、その聖歌をもとに生み出された新たな音楽、オルガヌムを書き留めていく過程の中で、特定の作曲家の存在こそ知られていないが、理論家や、合唱長などによって使われるようになった。この時代には、ネウマ譜のみならず、先に述べたタジア譜や文字譜なども、多様に使われており、ある意味、記譜法の試行と選別の時期として、新たに作られた音楽様式に適した記譜法を模索した時代が、この11世紀であったといえのではなかろうか。記録と伝播が目的の音楽の記譜法が、学問としてのレベルにおいて、検証され、時代を先取って言えば、作曲法の基礎として使われたことは注目に値する。だとすれば、記譜というものが、「記述的」から「規範的」に変わる過渡期もこの時代に見い出すこともできるだろう。11世紀末から、オルガヌムの手写譜が比較的、多く現われるようになり、同時期にトルバドゥールなどの単旋律の中世歌曲の楽譜も、グレゴリオ聖歌の楽譜も増加する。完全な要因は分からないが、この時代、いかなる形態にせよ、楽譜を残すという意識が、西洋に現われ、それは、やがて、楽譜を書くという意識へと変貌していくのである。
さて、平行オルガヌムにせよ、自由オルガヌムにせよ、ヴォクス・プリンチパリスとヴォクス・オルガナリスは、一音対一音の関係で構成されていた。つまり、定旋律とそれに対応する他の対旋律の音価は、基本的に等しいことになる(譜例2-3a,b) 。それに対し、次の時代のオルガヌムは、定旋律の音符一個に、複数の音符からなる対旋律がつくようになった(譜例2-3c)。この革新のもっとも重要な資料が、フランス中央部リモージュにかつて存在したサン・マルシャル修道院でみつかっている[注26] 。リモージュは、アキテーヌ地方の中心地であり、ここには、アキテーヌ式ネウマで書かれた4冊の写本があった。この定旋律一音に対し、複数の音が歌われる方式は、その音の数が増え、華麗な動きを繰り広げるようになると、メリスマ様式[注27](譜例2-3d)とよばれるようになる。
。それに対し、次の時代のオルガヌムは、定旋律の音符一個に、複数の音符からなる対旋律がつくようになった(譜例2-3c)。この革新のもっとも重要な資料が、フランス中央部リモージュにかつて存在したサン・マルシャル修道院でみつかっている[注26] 。リモージュは、アキテーヌ地方の中心地であり、ここには、アキテーヌ式ネウマで書かれた4冊の写本があった。この定旋律一音に対し、複数の音が歌われる方式は、その音の数が増え、華麗な動きを繰り広げるようになると、メリスマ様式[注27](譜例2-3d)とよばれるようになる。
ここで、複雑なことが起こるのだが、当時の理論家は、このような、一音対複数の音からなる多声曲を、オルガヌムと呼び、旧来の平行・自由オルガヌムのようなものを、ディスカントゥスと呼んだ。ただし、オルガヌムという語は依然として、前者も含めたポリフォニー曲全体を指す時にも使われている。しかし、この狭義のオルガヌム様式によって、発生した出来事は、そのような字義的解釈よりはるかに複雑であったにちがいない。なぜなら、狭義のオルガヌム様式とは、すなわち、音価の違う音が幾重にも重なりあうということを意味するからである。ここまできて、単に響きを強力にするだけではなく、二つ以上の声部が、それぞれ独立して動く、いわゆるポリフォニー polyphony[注28] は、産声をあげたといえる。声部の数が増え、各声部の独立性が高まり、結果として、リズムの対比という技巧が、音楽の中心的興味の範疇にとりいれられることになった。そして、リズムを中心課題とする音楽様式は、ノートルダム楽派のポリフォニーとなって、新たな記譜法を生み出す大きな推進力となった。ギリシアにおける、韻律の音楽的崩壊に変わる、そしてそれ以上のリズム表記への必要性は、ポリフォニーの誕生とともに確立されたわけである。
3.モーダル記譜法
音価を表示するということは、いくつかの音の持続の長さを表わすということである。音楽上の必要にせまられて、この方法を模索する歴史は、12世紀後半ごろから始まり、15世紀後半に、一応の終結をみる。その歴史を追う前に、多声音楽が、なぜ、音価の表示された楽譜を必要とするかについて、考えるべきであろう。まず、音価の表示は、何故、必要とされるのであろうか。それは、先にも述べた多声音楽の様式が、時間の構造体という側面をもっているからである。多声音楽は同時に進行するいくつもの声部からなり、それらの声部間は、密接な時間的連携をとる必要がある。誰もが、等しい時間の標準を持ち、同じ単位で調整されなくてはならない。そして、次に、楽譜が書かれる必要性だが、それは、当然、この種の音楽の複雑さに起因する。ここへきて、多声音楽は、音楽面で即興性から乖離し、記譜面で覚え書きから昇華し、一人の超越的存在による構成品となったのである。
まず、1200年前後、パリを中心に、今日ノートルダム楽派と呼ばれる音楽家たちが、大きな一歩を踏み出した。そこで活躍した、超越的存在は、個々の構成品(作品)に、作者の名がついているという点で、歴史上、初の作曲家となったレオニヌス Leninus (1163-1190ごろ活躍)とその後継者ペロティヌスPerotinus(c.1160-c.1220)である。
彼等が、音価を表示するために考えた方法は、モーダル記譜法 modal notation と呼ばれている。ノートルダム楽派は、まず、リズム・モード rhythmic modes[注29]というものを定義づけた。これは、簡単にいえば、長い音と短い音の区別をし、その組み合わせからなるある特定の形を前もって定義しておこうというものだった。音の長短という区別が、それまでなかったわけではないが、それは、単純な意味での長短であって、例えば、長と短が2:1になるというような相対的かつ表示可能なものではなかった[注30] 。彼等は、ネウマの中で、もっとも基本的な、ヴィルガとプンクトゥム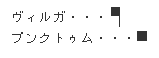 を、それぞれ、長音であるロンガ longa と短音であるブレヴィス brevis にあてた。ヴィルガは、もともと音の上昇をしめす。感覚的に、高めの音は、声を張り上げるので、ヴィルガは長めに演奏される習慣もあったという。さらに、相対的に音価を表記するためには、音の長さに一つの基準を与える必要がある。その基準をテンプス tempus(「時間」の意)と呼び、後のタクトゥス tactus(「拍」の意)[注31]
を、それぞれ、長音であるロンガ longa と短音であるブレヴィス brevis にあてた。ヴィルガは、もともと音の上昇をしめす。感覚的に、高めの音は、声を張り上げるので、ヴィルガは長めに演奏される習慣もあったという。さらに、相対的に音価を表記するためには、音の長さに一つの基準を与える必要がある。その基準をテンプス tempus(「時間」の意)と呼び、後のタクトゥス tactus(「拍」の意)[注31]  と同様の概念で用いた。そのテンプスに相当する長さが、ロンガであり、より短い音価を得るために、テンプスを三等分した短いものがブレヴィスになる。三位一体の思想に基づき三等分したわけだが、この方法だと、ロンガを1の音価とした場合、その分割型であるブレヴィスには1/3と2/3という二つの長さが存在することになる。しかし、音符はロンガとブレヴィスしかない。例えば、「ロンガ−ブレヴィス−ブレヴィス−ロンガ」という音符の並びにおいて、内側の二つのブレヴィスは、三等分の原則により、1/3と2/3にテンプスを分けあわなければならない。ロンガも状況により、このような変価を被る。これらを二倍化 alteratio[注32] や不完全化imperfectio(譜例2-4)と呼ぶが、こういった不規則性は三分割法が続く限り、永遠につきまとうものである。この矛盾を解決する方法が、まさにリズム・モードなのである。もともと、ロンガやブレヴィス、テンプスといった言葉は、アリストテレスの『音楽論 De Musica 』にあらわれるもので、そこには、28種類の韻脚が上げられており、ノートルダム学派が、規定した6つのモード(譜例2-5)
と同様の概念で用いた。そのテンプスに相当する長さが、ロンガであり、より短い音価を得るために、テンプスを三等分した短いものがブレヴィスになる。三位一体の思想に基づき三等分したわけだが、この方法だと、ロンガを1の音価とした場合、その分割型であるブレヴィスには1/3と2/3という二つの長さが存在することになる。しかし、音符はロンガとブレヴィスしかない。例えば、「ロンガ−ブレヴィス−ブレヴィス−ロンガ」という音符の並びにおいて、内側の二つのブレヴィスは、三等分の原則により、1/3と2/3にテンプスを分けあわなければならない。ロンガも状況により、このような変価を被る。これらを二倍化 alteratio[注32] や不完全化imperfectio(譜例2-4)と呼ぶが、こういった不規則性は三分割法が続く限り、永遠につきまとうものである。この矛盾を解決する方法が、まさにリズム・モードなのである。もともと、ロンガやブレヴィス、テンプスといった言葉は、アリストテレスの『音楽論 De Musica 』にあらわれるもので、そこには、28種類の韻脚が上げられており、ノートルダム学派が、規定した6つのモード(譜例2-5)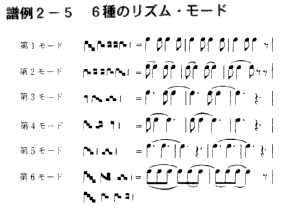 と対応している。リズム・モードと古典詩の韻脚を結び付けて論じた記録は、13世紀末のイングランドの理論家ウォルター・オディントン Walter Odington の手になるものだが、おそらく、中世の学者が、意図的にこの韻脚を借用したと考えるほうが、自然であろう。
と対応している。リズム・モードと古典詩の韻脚を結び付けて論じた記録は、13世紀末のイングランドの理論家ウォルター・オディントン Walter Odington の手になるものだが、おそらく、中世の学者が、意図的にこの韻脚を借用したと考えるほうが、自然であろう。
例えば、第一モードは、長−短の組み合わせで、トロケウス trochaeusと呼ばれる。第二モードは、短−長の組み合わせで、イアンブス iambusと呼ばれる。そして、この小さい単位をオルドーと呼び、繰り返される。そして、このモードの決定には、独特の方法が用いられた。ノートルダム楽派は、譜線付きネウマをもとに(譜線の数は4本から5本)、ネウマの形を徐々に角形にし、リガトゥラと呼ばれるいくつかのネウマが密着した形で表示される連結符を基本的に用いた。このリガトゥラに含まれるネウマの数とその順序で、6つのリズム・モードを弁別したわけである。例えば、3音リガトゥラの後に、2音リガトュラがつづけば、第一モードを示すのである。つまり、モーダル記譜法は音符一つ一つの長短を示すのではなく、モードの種類を模式的に表示することによって、間接的に音に長短の差を与える記譜法なのである。旋律を文字で記号化するのが、動機譜であるが、モーダル記譜法では、音価を、この場合リズムをリガトュラの連なりで記号化しているともいえよう。動機譜がそうであったように、空間的な可視化とは無縁のものである[注33]。まず、そのモードの了解が前提となるからである。
したがって、モーダル記譜法にはいくつもの欠点がある。原理はいたって単純なのだが、ノートルダム学派の楽曲の中で、この原理だけで解読できる曲が一曲もないという事実がそのことを示している。もともと多声音楽の様式は、リズムの変化にその音楽的興味の重点をおくことを目指していた。したがって、この学派の音楽は、いくつものモード間の移行や、装飾音の使用、そしてモードの変形によるリズムの変化に特徴をおくものであった。したがって、前もってリズム・モードを熟知し、的確に判断していったとしても、動機譜の単純な概念には、記譜される音楽が複雑すぎるのである。ノートルダム楽派の創始者的な存在であるレオニヌスのあるオルガヌム作品では、狭義のオルガヌムとディスカントゥスが一つの作品の中で対比的に扱われている。これは当時一般的な構成方法でもある。しかし、明確なリズム・モードで歌われるディスンカント部(クラウズラ部とも呼ばれた)はよくても、テノール(第一声部)[注34] が、オルゲルプンクト[注35]状にグレゴリオ聖歌の旋律を持続し、その上で、ドゥプルム(第二声部)[注36] が波打つような細かい動きで歌うオルガヌム部(または、持続音様式部)のメリスマティックな旋律には、リズム・モード的に不規則、不統一のリガトゥラの配列が多く見られる。こういった部分に、今日、一定の解釈をあてはめることは不可能である。
では、これらの欠点を打開するには、どのような記譜法に頼れば良いのだろうか。それは、リズム・モードを知らなくても読むことが可能で、リズム・モードに従わないリズムでも作曲が可能になる記譜法である。こういった時代の要請にこたえられる体系が、定量譜と呼ばれる、音価表示方法なのである。
第2章、続く