第2章「楽譜の本質」 続き
4.モテトゥスとフランコ式記譜法
13世紀、オルガヌムに変わって登場し、16世紀に至るまで、西洋音楽の重要なジャンルとなる形式がモテトゥスである。非常にややこしいのだが、オルガヌムの中から、当時人気のあったディスカントゥス様式の部分を取り出したものをクラウズラと呼ぶ。狭義のオルガヌム様式は、メリスマティックになると先に説明したが、メリスマ的な部分は、聖歌の中にも存在し、そのような部分を定旋律としてオルガヌムを作ると、ディスカントゥス様式となる場合が多い。したがって、クラウズラは、全ての声部がメリスマで歌われる。そして、定旋律とまったく同じリズムになる対旋律に新たな歌詞をつけたものを「言葉付き」という意味でモテトゥスと呼ぶようになった。つまり、別の歌詞が同時に歌われるのだが、注意しなければいけないのは、定旋律はメリスマで歌われたのに対し、対旋律は一音対一シラブルであったという点だ。今まで、リズム・モードの表示に借用されてきたリガトゥラは、一つの音符ごとに、一つのシラブルを付けなければならなくなり、分割されざるを得なくなる。つまり、このモテトゥスの声部は、リズム・モードの表記が不可能になってしまうのだ。特に、モテトゥスの独立性が高くなり、もとのクラウズラやディスカントゥスが不明になると、音符ごとの音価を、その音符によって指示しなければならない必要性がでてくるのである。この一つ一つの音符の形状で、音価を明示するという発想こそが、定量譜と呼ばれるものなのである。
すでに、ロンガとブレヴィスという二つの音符は別個に表示可能になっていた。さらに、ヨハネス・デ・ガルランディア Johannes de Garlandia(1240年頃活躍)の『計量音楽論 De mensurabili musica』において、ロンガより長いドゥプレクス・ロンガ、ブレヴィスより短いセミブレヴィス が説明されている。しかし、これらの関係をより明解に説明したのが、「偽アリストテレス」の名で知られるマギステル・ランベルトゥス Magister Lambertusでった。彼は、1270年頃『音楽論 Tractatus de musica』を記し、3分割の原則からおこるロンガやブレヴィスの変価の法則を説明した。彼は、基本的音価の単位、テンプスをブレヴィスにおいた。そして、徐々に定量化への道を進んでいく記譜法の変遷は、ケルンのフランコ Franco de Coloniaの『計量音楽技法 Ars cantus mensurabilis』[注37] によって体系化された。これを特に、フランコ式記譜法と呼ぶ。彼は、ロンガとブレヴィスの関係を明確にし、休止符やリガトゥラの音価の固定と記号を統一した。また、ロンガとブレヴィスの関係が、ブレヴィスとセミブレヴィスにも成り立つとした。
が説明されている。しかし、これらの関係をより明解に説明したのが、「偽アリストテレス」の名で知られるマギステル・ランベルトゥス Magister Lambertusでった。彼は、1270年頃『音楽論 Tractatus de musica』を記し、3分割の原則からおこるロンガやブレヴィスの変価の法則を説明した。彼は、基本的音価の単位、テンプスをブレヴィスにおいた。そして、徐々に定量化への道を進んでいく記譜法の変遷は、ケルンのフランコ Franco de Coloniaの『計量音楽技法 Ars cantus mensurabilis』[注37] によって体系化された。これを特に、フランコ式記譜法と呼ぶ。彼は、ロンガとブレヴィスの関係を明確にし、休止符やリガトゥラの音価の固定と記号を統一した。また、ロンガとブレヴィスの関係が、ブレヴィスとセミブレヴィスにも成り立つとした。
ランベルトゥスやフランコの定量記譜法では、ロンガを3種類、ブレヴィスを2種類、セミブレヴィスを2種類としている。列挙すると、
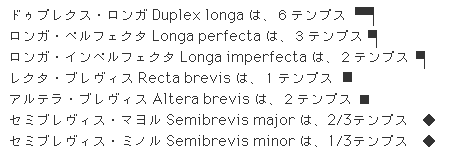
となる。彼等の功績は、すべての変種に固有の名前をつけ、どのようにしてそれが起こるかを説明したことにある。例えば、「ロンガ--ブレヴィス」とならぶと、このロンガは、不完全化をうけて、ロンガ・インペルフェクタとなる。「ロンガ--ブレヴィス--ブレヴィス--ロンガ」という配列の場合、ロンガがインペルフェクタなら、二番目のブレヴィスは、二倍化をうけてアルテラ・ブレヴィスとなる。同じ関係が、ブレヴィスとセミブレヴィスにもいえるわけである。
これらの、記譜法は、音符の関係を明確にすることで、リズムのモードをより正確に書き留めることを目的としていた。しかし、できあがった記譜法は、さまざまな変種の組合わせから、リズム・モードを超えた自由なリズムが表示できる可能性を秘めていた。つまり、音楽の変化が記譜法の変化であるばかりでなく、記譜法の変化が音楽の変化でもあるわけだ。時代の音楽は、教会だけでなく、世俗にも還元され、大学の発展とともに、多くの知識人たちの手に委ねられることとなった。「記述的」目的から発展してきた楽譜は、「規範的」に使用されるようになり、教会の典礼のためではなく、音楽をつくるという目的によって、楽譜の持つ潜在性を弾き出した音楽家たちは、遂にモーダル・リズムの体系を駆逐してしまうのである。14世紀にはいり、フィリップ・ド・ヴィトリ Philippe de Vitry (1291-1361)が著わした論文『アルス・ノヴァ Ars nova 』をめぐっておこった論争が、まさにそのことの象徴となるだろう。
5.アルス・ノヴァと譜法の近代化
1325年ごろ著わされた『アルス・ノヴァ』は「新技法」と訳されてきたが、このアルスというのは、まさに記譜法のことを指す。この論文の15章以降の重要な部分において、ヴィトリは、それまでの不完全な記譜法に対し、もっと精密な記譜法を提唱しているのである。この論文に由来してこの時代の記譜法をフランス・アルス・ノヴァ記譜法[注38] 、あるいは、黒符定量記譜法と呼んでいるが、その説明は『アルス・ノヴァ』よりも、ヨハネス・デ・ムリス Johannes de Muris(ジャン・デ・ミュール Jehan des Murs1300-1350)の『計量音楽の書 Libellus cantus mensurabilis 』に詳しい。
これらの記譜法で成し遂げられたものは、第一にセミ・ブレヴィスの独立である。フランコにおいても、それは容認されていたが、理論上のことで、音楽的には実現されていなかった。この点を、ジャック・ド・リエージュ Jacques de Li使e(c.1260-c.1340)は『音楽の鏡 Speculum musicae 』において、非難している。伝統的な書法では、ブレヴィスはセミブレヴィスに完全分割されるだけだった。つまり、三分割である。ところが、アルス・ノヴァ派は、さらに、セミブレヴィスの下に、ミニマ minima という音符をおき、分割方法も、始めて不完全、つまり二分割を認めたのである。ここでの分割は二等分を意味し、これにより、民衆音楽ではなく、教会音楽、芸術音楽の中に、二拍子や四拍子が導入されたことになる。では、少し、詳しく、「アルス・ノヴァ」の記譜法をみていこう。
という音符をおき、分割方法も、始めて不完全、つまり二分割を認めたのである。ここでの分割は二等分を意味し、これにより、民衆音楽ではなく、教会音楽、芸術音楽の中に、二拍子や四拍子が導入されたことになる。では、少し、詳しく、「アルス・ノヴァ」の記譜法をみていこう。
この時代、タクトゥス(テンプスと同義)は、セミブレヴィスに移っていた。音符は長いほうからマキシマ maxima、ロンガ、ブレヴィス、セミブレヴィス、ミニマの五種類に拡大された。変価を伴う音符を個別の名前で呼ばず、それぞれの音価の間の関係を以下のように、個別に命名した。
マクシマとロンガの関係は、マクシモドゥス Maximodus
ロンガとブレヴィスの関係は、モドゥス Modus
ブレヴィスとセミブレヴィスの関係は、テンプス Tempus
セミブレヴィスとミニマの関係は、プロラツィオ Prolatio
これら全ての関係において、完全(三分割)と不完全(二分割)が事実上、平等になされるのである。ただし、楽曲上、問題となるのは、ブレヴィス以下のテンプスとプロラツィオであった。例えば、ブレヴィスが3つのセミ・ブレヴィスに等分される場合、それは完全テンプス tempus perfectum と呼ばれ、そのセミ・ブレヴィスが2つのミニマに分割されるなら、不完全プロラツィオ prolatione imperfecta ということになる。つまり、分割方法の組み合わせは以下の四種類が考えられる。

という四種類のリズムができることになる。この分割方法の四通りのパターンを、当時の理論家は明確な記号に表わすため、様々な方法を試行した。最終的に、完全テンプスは円、不完全テンプスは右側の欠けた半円で表わし、完全プロラツィオは円の中に点をうち、不完全はそのままとすることになった。この記号をメンスーラ記号、つまり、計量記号と呼ぶ。現行の記譜法で、4/4拍子を表わすC記号は、アルファベットのCで代用されているが、実際は、右側の欠けた半円である。つまり、その曲のメンスーラーが不完全テンプス不完全プロラツィオであることを示すために、譜線の左端に書かれた当時の用法の名残なのである[注39] 。
さて、アルス・ノヴァ以前から、例えば、隣り合うブレヴィスを、それぞれ別の数のセミブレヴィスに分割したい時、その区切り目を表わすために、分割点 punctus divisionis が使われるようになっていた。これは、12世紀末に活躍したペトルス・デ・クルーチェ Petrus de Cruce (Pierre de la Croix 1290頃活躍)によって、導入されたという説が有力である。フランコは、ブレヴィスのセミブレヴィスへの分割を2〜3分割としていたが、クルーチェは、それをこの分割点の用法と合わせ7分割にまで広げた。この分割点は、並びあう音符の区切りを明確にし、二倍化や不完全化を促進したり、回避したりする。アルス・ノヴァでも、完全分割の際にだけおこる二倍化や不完全化に分割点は使われる。しかし、二倍化や不完全化のおこらない不完全分割にも、この点は存在し、それは音符の音価を1/2 引き伸ばすという今日の付点にあたる役割をした。この新しい点 puncutus additionis の使用は、さらに、複雑なリズム表記を可能にした。さらに、これは近代の記譜法にはないものだが、色符あるいは赤符 colar [注40] という赤いインクで書かれた音符は、通常の音符を2/3 に縮小することを意味し、ヘミオラ効果[注41] という用法に使われた。
アルス・ノヴァはほとんど、近代の記譜法に接近している。その違いは、三分割という方法をとっている点と、小節という概念が存在しない点にある。この後、楽譜は、近代の我々が知る記譜法に向かって進んでいく。もはや、楽譜に対する概念は、西洋の音楽家にとって共通の、規範となるものに成長している。これまで、見てきたように、ノートルダムから、アルス・ノヴァまで、記譜法はおおむねフランスを舞台に発展してきた。このフランスの記譜法は、イギリスやドイツでも使われていた。イタリアの記譜法はそれとは別に、注目に値する。  14世紀、イタリアの音楽は、イタリア語で300を意味するトレチェントという言葉から、トレチェント音楽と呼ばれている。彼等の記譜法は、フランスの初期の定量譜法を基礎としており、クルーチェ式の分割点の使用によっていた。彼等はブレヴィスを6通りに分割し、それぞれに名称を与え、省略記号でそれを示したが、アルス・ノヴァに可能な複雑なリズムを表示することはできなかった。ただ、彼等は、音符の符尾を変化させることでリズムの変化を表示する方法を確立した。これは、現在の音符の「旗」に類似しいる。さらに、音符2個分のスペースに3個の音符を挿入するという、今日の三連符とまったく同質のものも存在した。そして、15世紀ごろからイタリアを中心に使われていたと思われる鍵盤楽器のためのタブラチュア譜は、近代の五線譜法に極めて接近している。今まで、見てきた記譜法が、実は声楽のためのものであったことを忘れてはならない。器楽のための記譜法、タブラチュアの存在には先に触れたが、14世紀ごろから、明確に両者を区別していたようだ。ただ、中世の器楽曲の楽譜は、稀少であり、画一的な見解は述べられていない。しかし、この時代の鍵盤のタブラチュアは、スコア状の書法をとり、上段と下段の垂直関係を示すため、小節線が用いられていることが目にとまる[注42](譜例2-6) 。15世紀後半から16世紀にかけてギョーム・デュファイ Guillaume Dufay(c.1400-1474)やジョバンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナ Giovanni Pierluigi da Palestrina(c.1525-1594)らルネサンスの音楽作品を数多く記した白符計量記譜法よりも、近代の五線譜に近い形態を示している。これは、トレチェントの分割点の使用法--それは専ら小節線的に使われていたわけだが--による所が大きいだろう。この例に関しては、15世紀初頭の《レーナ手写本》と《ファエンツァ手写本》以降、100年間、見られない譜法である。ルネサンスも、声楽の時代であったから、声楽向きに発展してきた楽譜がほとんどであったのだろう。
14世紀、イタリアの音楽は、イタリア語で300を意味するトレチェントという言葉から、トレチェント音楽と呼ばれている。彼等の記譜法は、フランスの初期の定量譜法を基礎としており、クルーチェ式の分割点の使用によっていた。彼等はブレヴィスを6通りに分割し、それぞれに名称を与え、省略記号でそれを示したが、アルス・ノヴァに可能な複雑なリズムを表示することはできなかった。ただ、彼等は、音符の符尾を変化させることでリズムの変化を表示する方法を確立した。これは、現在の音符の「旗」に類似しいる。さらに、音符2個分のスペースに3個の音符を挿入するという、今日の三連符とまったく同質のものも存在した。そして、15世紀ごろからイタリアを中心に使われていたと思われる鍵盤楽器のためのタブラチュア譜は、近代の五線譜法に極めて接近している。今まで、見てきた記譜法が、実は声楽のためのものであったことを忘れてはならない。器楽のための記譜法、タブラチュアの存在には先に触れたが、14世紀ごろから、明確に両者を区別していたようだ。ただ、中世の器楽曲の楽譜は、稀少であり、画一的な見解は述べられていない。しかし、この時代の鍵盤のタブラチュアは、スコア状の書法をとり、上段と下段の垂直関係を示すため、小節線が用いられていることが目にとまる[注42](譜例2-6) 。15世紀後半から16世紀にかけてギョーム・デュファイ Guillaume Dufay(c.1400-1474)やジョバンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナ Giovanni Pierluigi da Palestrina(c.1525-1594)らルネサンスの音楽作品を数多く記した白符計量記譜法よりも、近代の五線譜に近い形態を示している。これは、トレチェントの分割点の使用法--それは専ら小節線的に使われていたわけだが--による所が大きいだろう。この例に関しては、15世紀初頭の《レーナ手写本》と《ファエンツァ手写本》以降、100年間、見られない譜法である。ルネサンスも、声楽の時代であったから、声楽向きに発展してきた楽譜がほとんどであったのだろう。
そのルネサンス期、15世紀後半から、16世紀にかけての記譜法である白符計量記譜法(譜例2-7) は、アルス・ノヴァを基礎にしたものだが、特に、新しい技法が加わりはしない。いままで、黒符だったものが、白抜きの音符に変ったことが目につくが、それも、従来の羊皮紙にかわり、インクののりが良い紙が一般化したため、音符を塗りつぶす必要がなくなったことに起因する。つまり、この時代の記譜法は、15世紀前半に、過度に複雑化し、煩瑣なものとなった技法を消化し、明快な記譜法として、洗練させていったものなのである。しかし、この記譜法では、デュファイやパレストリーナの他に、ジョスカン・デ・プレ Josquin des Prez(c.1440-1521)、オルランド・ディ・ラッソ Orlando di Lassoらの芸術的かつ音楽史的価値の高い楽曲が残されており、西洋記譜法が一旦たどり着いた完成型として、その存在を軽く扱うことはできない。
は、アルス・ノヴァを基礎にしたものだが、特に、新しい技法が加わりはしない。いままで、黒符だったものが、白抜きの音符に変ったことが目につくが、それも、従来の羊皮紙にかわり、インクののりが良い紙が一般化したため、音符を塗りつぶす必要がなくなったことに起因する。つまり、この時代の記譜法は、15世紀前半に、過度に複雑化し、煩瑣なものとなった技法を消化し、明快な記譜法として、洗練させていったものなのである。しかし、この記譜法では、デュファイやパレストリーナの他に、ジョスカン・デ・プレ Josquin des Prez(c.1440-1521)、オルランド・ディ・ラッソ Orlando di Lassoらの芸術的かつ音楽史的価値の高い楽曲が残されており、西洋記譜法が一旦たどり着いた完成型として、その存在を軽く扱うことはできない。
さて、先の《レーナ手写本》と《ファエンツァ手写本》から、一世紀がたち、1517年、アンドレア・アンティコ Andrea Antico (c.1480-1539以降)刊行の《フロットーラ・オルガン用編曲集Frottole intabulate de sonare orgni 》という最古のオルガン譜として、鍵盤譜法は復活し、これを皮切りに、16世紀から17世紀のイタリア、イギリス、フランスに広まるようになり、鍵盤から、弦や管楽器にも用いられるようになり、やがて、声楽にもその使用を容認される。そして、17世紀から18世紀にかけての間に、他の定量譜法やタブラチュアを文字通り、押し退けて、その後の西洋音楽を文字通り席巻することになる。それは、この記譜法が他のものより優れていたからではない。先に述べたように、音楽様式が、それに見合った記譜法を選択しただけである。15世紀から器楽音楽の隆盛がはじまり、17世紀から20世紀に支配的な音楽ジャンルになることは、周知のとおりである。つまり、ここで、近代五線譜法が、支配的な記譜法になったということは、定石通り、近代五線譜法を要求する音楽様式が生まれたということを意味するのである。
6.バロックと近代五線譜法の成立
現在では、西洋音楽の歴史は、美術史の用語を借りて示す方法が一般的である。古代、中世は、別としても、その後に続く、ルネサンス音楽、バロック音楽、古典派・ロマン派の音楽などがそれにあたり、これらの音楽の歴史は、だいたい150年というきりの良い数字を単位に転換をすると考えるとわかりやすい[注43]。ルネサンスの始まりは、その最も代表的な作曲家ギョーム・デュファイが活躍した1450年前後からはじまり、1600年を境いに、その黄金時代をバロック音楽に譲る。そして、バロック音楽の終焉は、やはり、150年後、この音楽の最後にして最大の巨匠、J.S.バッハの没年、1750年をもって、向かえられる。この17世紀から、18世紀にかけての時代は、先に述べたとおり、近代譜法がそれまでの声楽などの記譜法を席巻する時代である。いままでに、音楽様式の変遷が、記譜法の歴史を塗りかえると言明してきたが、ここにきて、西洋音楽は、近代譜法を必要とする新たな変化をとげる。それは、一言で言えば、「ポリフォニー」から「ホモフォニー」への変遷と言えるだろう。バロックという芸術の様式を詳述することは避けるが、バロック音楽の最も代表的なジャンルが、オペラであるように、バロック芸術の原理は、劇(ドラマ)に支配されている。バロック音楽のはじまりの時期を1600年としているのは、この年が、今日に残されている限りでの、最古のオペラ、ヤコポ・ペーリ Jacopo Peri (1561-1633) とジュリーオ・カッチーニ Giulio Caccini(c.1550-1618) の共作による《エウリディチェ L'Euridice》の上演の年だからである[注44]。これは、あくまでも象徴に過ぎないが、このオペラという形式も、ポリフォニーのホモフォニーへの変化に重要な基点を持っている。
ホモフォニーとは、辞書的に説明すれば、和声的様式の音楽を指す。たとえば、主声部を他の諸声部が一体化して和声的に支えるといった様式である。少し横暴に言ってしまえば、旋律と伴奏の音楽ということになるだろう。すなわち、各声部の独立性を主眼とするポリフォニー音楽とは、概念的に相反する音楽様式と言うことになる。
基本的なバロック音楽は、旋律と、伴奏楽器の最低声部からなる。譜例2-8a は、イタリアの後期バロックの大家アルカンジェロ・コレルリ Arcangelo Corelli(1653-1713) のヴァイオリンのためのソナタ作品5−8から、サラバンド楽章の冒頭の部分である。上段は、この場合、ヴァイオリンで奏される旋律であり、B.C.と書かれた下段は、チェンバロやオルガンといった鍵盤奏者が演奏する伴奏になるわけだが、この二声部は、書法的にポリフォニックと言える。少なくとも、ホモフォニーの意味する、和声的な支えというのはどこにも見当たらない。ここで、注目すべきなのが、下段の音符にしばしば付される数字や記号である。B.C.とはbasso continuoの略で、普通、通奏低音[注45] と言われるものである。通奏低音に付された数字や記号は、鍵盤奏者が、そのバス声部の上にどのような和音を付け加えて演奏するかを示す和音の略記法[注46] である。数字は、それが記された音の、調の内部での音程上の音を付加することを意味する。譜例2-8aの3小節目のFis音に付された5と6は、それぞれfisの5度上と、6度上の音を足すことを意味するから、鍵盤奏者は、そこに、CとDの音を補足する必要がある。譜例2-8bは、その演奏例である。3度上のA音は、当然付けるべきものとして、数字では書かれない。バロック音楽の通奏低音では、数字が記されていなくても、鍵盤奏者は即興的に伴奏を付ける。したがって、譜例2-8b には、数字で示されていない様々な音を見い出すことができるだろう。さらに、この最低音部は、チェロやファゴットなどの楽器によって重複して奏されるので、この記譜法では、二声部の楽譜は、三人(以上)で、三声部の楽譜は、四人(以上)の奏者で演奏されることになる。つまり、通奏低音では、譜面上にない、あるいは、数字などで略記された和音が、旋律を支えるホモフォニックな音楽ということになる。逆に言えば、このホモフォニーを通奏低音という仕組が、体系化し、構造づけたともいえるのではなかろうか。これら器楽音楽とともに、バロックの主要ジャンルたるオペラも、歌と伴奏という点で、ホモフォニーの構造なくしては、存在しないジャンルと言えよう。そして、この時代の音楽的興味は、器楽音楽の中にも、重要な形式を生み出した。それは、協奏曲である。協奏曲には、少数の独奏者のグループ、コンチェルティーノ concertinoと全体の合奏、リピエーノ ripienoからなる合奏協奏曲、コンチェルト・グロッソ concerto grossoと、一人の独奏者、ソロ soloと、全体の合奏からなる独奏協奏曲[注47] があるが、いずれも、強弱の、音色の、そして数の対比を徹底的に好む。つまり、リズムのもつれあう複雑な動きは、ポリフォニーとともに、音楽的興味から没落し、むしろ、劇的な音の対比がその中心となったのである。リズムが、複雑でなくなった分、メンスーラ記号による複雑な拍子の交代や分割は、無用になり、一定の拍子、一定のテンポで進む明快な音楽が主流となった。近代譜法にいたって、ようやく、完全分割と呼ばれてきた、実際はさまざまな意味で不完全な三分割は廃され、不完全化や二倍化の様な変価や、分割点の用例は存在しなくなった。そして、17世紀に入って、小節線が一般化され、これで、バロックの終焉と共に、通奏低音が使われなくなれば、現代の我々が目にする楽譜と呼ぶものと、ほとんど差のない記譜法が誕生することになる。この我々に最も馴染みのある記譜法の理論的な説明をすることは、楽典の復習にしかならないので、ここではとりあげず、一貫した記譜法の変遷にひとまずの結びをつけたいと思う。その後の記譜法については、後続の章で、近代記譜法の問題点とともに、また別の角度から見ることになるだろう。
は、イタリアの後期バロックの大家アルカンジェロ・コレルリ Arcangelo Corelli(1653-1713) のヴァイオリンのためのソナタ作品5−8から、サラバンド楽章の冒頭の部分である。上段は、この場合、ヴァイオリンで奏される旋律であり、B.C.と書かれた下段は、チェンバロやオルガンといった鍵盤奏者が演奏する伴奏になるわけだが、この二声部は、書法的にポリフォニックと言える。少なくとも、ホモフォニーの意味する、和声的な支えというのはどこにも見当たらない。ここで、注目すべきなのが、下段の音符にしばしば付される数字や記号である。B.C.とはbasso continuoの略で、普通、通奏低音[注45] と言われるものである。通奏低音に付された数字や記号は、鍵盤奏者が、そのバス声部の上にどのような和音を付け加えて演奏するかを示す和音の略記法[注46] である。数字は、それが記された音の、調の内部での音程上の音を付加することを意味する。譜例2-8aの3小節目のFis音に付された5と6は、それぞれfisの5度上と、6度上の音を足すことを意味するから、鍵盤奏者は、そこに、CとDの音を補足する必要がある。譜例2-8bは、その演奏例である。3度上のA音は、当然付けるべきものとして、数字では書かれない。バロック音楽の通奏低音では、数字が記されていなくても、鍵盤奏者は即興的に伴奏を付ける。したがって、譜例2-8b には、数字で示されていない様々な音を見い出すことができるだろう。さらに、この最低音部は、チェロやファゴットなどの楽器によって重複して奏されるので、この記譜法では、二声部の楽譜は、三人(以上)で、三声部の楽譜は、四人(以上)の奏者で演奏されることになる。つまり、通奏低音では、譜面上にない、あるいは、数字などで略記された和音が、旋律を支えるホモフォニックな音楽ということになる。逆に言えば、このホモフォニーを通奏低音という仕組が、体系化し、構造づけたともいえるのではなかろうか。これら器楽音楽とともに、バロックの主要ジャンルたるオペラも、歌と伴奏という点で、ホモフォニーの構造なくしては、存在しないジャンルと言えよう。そして、この時代の音楽的興味は、器楽音楽の中にも、重要な形式を生み出した。それは、協奏曲である。協奏曲には、少数の独奏者のグループ、コンチェルティーノ concertinoと全体の合奏、リピエーノ ripienoからなる合奏協奏曲、コンチェルト・グロッソ concerto grossoと、一人の独奏者、ソロ soloと、全体の合奏からなる独奏協奏曲[注47] があるが、いずれも、強弱の、音色の、そして数の対比を徹底的に好む。つまり、リズムのもつれあう複雑な動きは、ポリフォニーとともに、音楽的興味から没落し、むしろ、劇的な音の対比がその中心となったのである。リズムが、複雑でなくなった分、メンスーラ記号による複雑な拍子の交代や分割は、無用になり、一定の拍子、一定のテンポで進む明快な音楽が主流となった。近代譜法にいたって、ようやく、完全分割と呼ばれてきた、実際はさまざまな意味で不完全な三分割は廃され、不完全化や二倍化の様な変価や、分割点の用例は存在しなくなった。そして、17世紀に入って、小節線が一般化され、これで、バロックの終焉と共に、通奏低音が使われなくなれば、現代の我々が目にする楽譜と呼ぶものと、ほとんど差のない記譜法が誕生することになる。この我々に最も馴染みのある記譜法の理論的な説明をすることは、楽典の復習にしかならないので、ここではとりあげず、一貫した記譜法の変遷にひとまずの結びをつけたいと思う。その後の記譜法については、後続の章で、近代記譜法の問題点とともに、また別の角度から見ることになるだろう。
第3章へ
14世紀、イタリアの音楽は、イタリア語で300を意味するトレチェントという言葉から、トレチェント音楽と呼ばれている。彼等の記譜法は、フランスの初期の定量譜法を基礎としており、クルーチェ式の分割点の使用によっていた。彼等はブレヴィスを6通りに分割し、それぞれに名称を与え、省略記号でそれを示したが、アルス・ノヴァに可能な複雑なリズムを表示することはできなかった。ただ、彼等は、音符の符尾を変化させることでリズムの変化を表示する方法を確立した。これは、現在の音符の「旗」に類似しいる。さらに、音符2個分のスペースに3個の音符を挿入するという、今日の三連符とまったく同質のものも存在した。そして、15世紀ごろからイタリアを中心に使われていたと思われる鍵盤楽器のためのタブラチュア譜は、近代の五線譜法に極めて接近している。今まで、見てきた記譜法が、実は声楽のためのものであったことを忘れてはならない。器楽のための記譜法、タブラチュアの存在には先に触れたが、14世紀ごろから、明確に両者を区別していたようだ。ただ、中世の器楽曲の楽譜は、稀少であり、画一的な見解は述べられていない。しかし、この時代の鍵盤のタブラチュアは、スコア状の書法をとり、上段と下段の垂直関係を示すため、小節線が用いられていることが目にとまる[注42](譜例2-6) 。15世紀後半から16世紀にかけてギョーム・デュファイ Guillaume Dufay(c.1400-1474)やジョバンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナ Giovanni Pierluigi da Palestrina(c.1525-1594)らルネサンスの音楽作品を数多く記した白符計量記譜法よりも、近代の五線譜に近い形態を示している。これは、トレチェントの分割点の使用法--それは専ら小節線的に使われていたわけだが--による所が大きいだろう。この例に関しては、15世紀初頭の《レーナ手写本》と《ファエンツァ手写本》以降、100年間、見られない譜法である。ルネサンスも、声楽の時代であったから、声楽向きに発展してきた楽譜がほとんどであったのだろう。
は、アルス・ノヴァを基礎にしたものだが、特に、新しい技法が加わりはしない。いままで、黒符だったものが、白抜きの音符に変ったことが目につくが、それも、従来の羊皮紙にかわり、インクののりが良い紙が一般化したため、音符を塗りつぶす必要がなくなったことに起因する。つまり、この時代の記譜法は、15世紀前半に、過度に複雑化し、煩瑣なものとなった技法を消化し、明快な記譜法として、洗練させていったものなのである。しかし、この記譜法では、デュファイやパレストリーナの他に、ジョスカン・デ・プレ Josquin des Prez(c.1440-1521)、オルランド・ディ・ラッソ Orlando di Lassoらの芸術的かつ音楽史的価値の高い楽曲が残されており、西洋記譜法が一旦たどり着いた完成型として、その存在を軽く扱うことはできない。