第1章 楽譜の本質
1.記譜の意味
「書かれた音楽の記号は音楽そのものでも音楽の写しでもなくただの覚え書きにすぎない。音楽は実際の音としてしか存在しない」というシオアンの言葉を先ほども引用したが、まさにそれは正鵠を得ている。確かに、「書かれた音楽の記号」、すなわち楽譜は音楽そのものではない。
「覚え書き」という言葉が、どれほどの意味で楽譜の価値を言明しているのかは分からないが、それでも、音楽を「可視化」することが、単なる「覚え書き」にすぎないと断言するのは、いささか性急にすぎるのではないだろうか。音楽の「可視化」は、実際、楽譜という形によって、極めて精密に成し遂げられてきた。したがって、まず、その歴史を考えながら、音楽を「可視化」することの意味や問題を探っていくべきであろう。
一般的に楽譜といえば、西洋の五線譜を第一のものと考えがちだが、音楽文化が爛熟した地域では、音楽の「可視化」は、古くから成し遂げられてきた。音楽記号学の世界では、楽譜は可視的な記号として、セミオグラフィに属す。しかし、その記号には「規範的 prescriptive」なものと「記述的 descrictive」なものがあり、この二つは、別の次元で考えなければならないという[注6] 。規範的な楽譜とは、作曲者によって書かれた楽譜であり、近代的言葉でいうなら、「作曲された」楽譜である。一方の記述的な楽譜とは、すでに音楽として存在する演奏を、楽譜という形で「記録した」ものである。これは、「採譜 transcription」[注7] といえば、分かりやすいかもしれない。音楽を可視化するということは、当然、その記譜された楽譜によってもとの音楽を知りうるようにすることである。その意味では、どちらの楽譜も、それをなし得る。できれば、その楽譜のみによって音楽を把握できることが望ましいが、厳密に考えれば、それは不可能である。では、膨大な音楽情報の中の一体、何を明確に記録できれば、その音楽は、楽譜によって知りうるようになり、再現できるのだろうか。近代の音楽観が導き出す答えは、音高 pitchと音価 note value、つまり音の高低と持続である。この二つを知ることによってさまざまな持続の連続をもった音列、つまりメロディーを知りうるからだ[注8] 。しかし、楽譜の歴史を概観して行けば、わかるように、これらの要素を正確に記述しうるものばかりが、楽譜と呼ばれているわけではない。したがって、記譜法の変遷は、西洋の場合、音高と音価を記号化する方法の獲得を、記譜法の発展として位置付けてきた。そして、それは、近代五線譜法と呼ばれる現在一般的に使われている楽譜へ至る長い歴史と考えられている。
西洋に限ったことではないが、音高の表示は、古い時代からある程度、厳密に行われていた。実際、音とは、高さ、長さ、強さ、そして音色の四つの属性によってなりたっている。音高の判断は、物理的現象、すなわち振動数の多い少ないということよりも、印象によるところが多い。強い音は、弱い音より高く感じるというように、ある属性は、他の属性との交わりの中で変化する。古代ギリシアでは、哲学的興味から、音階や、音程に対する理論的考察が行われていた。これは起源前6世紀ごろから記録があり、音階や音程を考察するために、まず音高の記号化が行われていた。これらは、世界の秩序を把握する上で、重要な数学的対象でもあった。
一方、音価とは、音の長さであるが、この属性には、二通りの解釈がなされうる。後続の章で語られる楽譜の歴史の中で、最初に我々が出会う音価とは、例えば、近代譜法なら、四分音符や八分音符で表わされるような相対的な音価である。これらの音の長さが、絶対的なものではないというのは、たとえば、演奏に際して、明確なテンポによって規定されてはいても、演奏家によってその長さも詰まったり、伸びたりすることでわかる。または、二分音符の音価が、文字通り二拍、つまり三拍目まで伸ばすことを意味するとして、三拍目に同じ音があったら、どういうことになるだろう。一瞬の隙間も空かずに、同じ音を連続することができるだろうか。楽器によっては、機能的にそれが不可能な場合もある。音符は、実は、打鍵のタイミングとその余韻を知らせているにすぎない。音の質を全く変えずに、音を持続できる楽器は、一般的には、存在しない。したがって、音価に完璧をもとめるならば、それは、電子音の登場を待つ必要がある。音価の二つ目の解釈がこの電子音響による絶対的音価である。
西洋記譜法の歴史では、音高の表示方法が、まず開拓され、その後は音価の表示方法に、変遷の焦点があてられることになる。現実として、この音価の表示方法の獲得は、西洋音楽の独自の進化を決定づけたといっても過言ではない。音価の表示方法を獲得したことに、西洋の記譜法の特徴があり、それは、音楽と記譜法の歴史にとっての特異点とも評せるからだ。
ただし、それらをすべからく、発展と看做すことはできない。たとえば、表示が不十分だからという理由で、別の記譜法を退ける行為は、西洋の近代的な発展史観に基づいているという誹りを免れないだろう。確かに、音高や音価を正確に記述すれば、それだけ音楽のより精度の高い再現が可能になる。しかし、記譜法は、その時代、地域の音楽様式と密接に関連しているのだから、ある時代の音楽観を、別の時代のそれに当てはめることができないように、楽譜を一つの形式から、近代的ではないという理由で、他の形式に移植[注9] することはできない。
2.記譜法の分類
まず、次にあげる分類は、特に西洋に限らず適用できるのだが、基本的な記譜法、つまり、なにかしらの形で音楽を記述しようと試みたものを、その記述している情報や形態に応じて分類したものである。また、ここに登場するいくつかの用語は、これから記譜法の変遷を見ていく上で、理解の一助になる基本的な言葉でもある。
例えば、記譜の初期の頃には、ある特定の旋律の形や、動機を文字であらわす方法があった。これは動機譜 ekphonetic notation (譜例1-1) と呼ばれ、ユダヤ教の聖歌[注10] 、および中世のビザンツ、シリア、アルメニアなどの聖歌に使われた方式である。この方法は、一つ一つの音に関しては、まったく記述されず、ある旋律型に固有の記号で図示しようという発想による。「記述的な」楽譜といえないこともないが、可視化という意味では、楽譜とは呼びにくい。まさに、記憶の中の旋律を呼び覚ますための「覚え書き」の役割にあると言えるだろう。この動機譜が、ほとんどすたれてしまったのに対し、これにとって代わる次の三つの形態は、姿を変えながらも、その歴史を存続させることになる。
と呼ばれ、ユダヤ教の聖歌[注10] 、および中世のビザンツ、シリア、アルメニアなどの聖歌に使われた方式である。この方法は、一つ一つの音に関しては、まったく記述されず、ある旋律型に固有の記号で図示しようという発想による。「記述的な」楽譜といえないこともないが、可視化という意味では、楽譜とは呼びにくい。まさに、記憶の中の旋律を呼び覚ますための「覚え書き」の役割にあると言えるだろう。この動機譜が、ほとんどすたれてしまったのに対し、これにとって代わる次の三つの形態は、姿を変えながらも、その歴史を存続させることになる。
文字譜 letter natation (譜例1-2)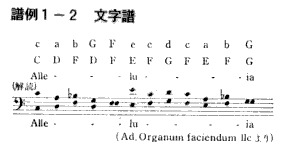 は、個々の音の高さを文字で示したものである。ヨーロッパでは、古代ギリシアなどに見られる。現代でも、音名によって音楽を記述することは出来る。「ドレミードレミーソミレドレミレー」などと書けば、その旋律は自ずと理解できる[注11] 。この体系では、上の例の「ー」のように、別の記号を用いなければ、音価を示すことは出来ない。
は、個々の音の高さを文字で示したものである。ヨーロッパでは、古代ギリシアなどに見られる。現代でも、音名によって音楽を記述することは出来る。「ドレミードレミーソミレドレミレー」などと書けば、その旋律は自ずと理解できる[注11] 。この体系では、上の例の「ー」のように、別の記号を用いなければ、音価を示すことは出来ない。
ネウマ譜 neuma (譜例1-3)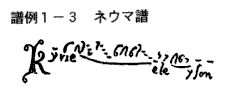 は、ネウマはグレゴリオ聖歌などの記譜法として知られており、旋律の上下行を特定の線状の記号であらわす方法である。ネウマ譜については、後続の章で十分触れる機会があるので、簡単な紹介にとどめるが、動機譜や文字譜が、旋律の動きや音高とは無関係な記号によって記述されているのに対し、ネウマ譜では、高い音を上、低い音を下と考える隠喩によって、旋律の動きが、空間的に可視化されている。これは、音符を使う唯一の記譜法であり、音高の可視化としては巨大な発明と言えるだろう。
は、ネウマはグレゴリオ聖歌などの記譜法として知られており、旋律の上下行を特定の線状の記号であらわす方法である。ネウマ譜については、後続の章で十分触れる機会があるので、簡単な紹介にとどめるが、動機譜や文字譜が、旋律の動きや音高とは無関係な記号によって記述されているのに対し、ネウマ譜では、高い音を上、低い音を下と考える隠喩によって、旋律の動きが、空間的に可視化されている。これは、音符を使う唯一の記譜法であり、音高の可視化としては巨大な発明と言えるだろう。
これらの形態と根本的に発想が異なるのが、タブラチュア tablature (譜例1-4) である。これは「奏法譜」と訳されるように、それぞれの楽器の演奏方法を文字や数字などの記号で記述したものであり、その楽器の弦や穴の位置が図示され、付された記号は、音高や音価を表わすのではなく、弦のどこを押さえるかとか、管楽器なら、穴のどこを塞ぐかということを記述するものである。
である。これは「奏法譜」と訳されるように、それぞれの楽器の演奏方法を文字や数字などの記号で記述したものであり、その楽器の弦や穴の位置が図示され、付された記号は、音高や音価を表わすのではなく、弦のどこを押さえるかとか、管楽器なら、穴のどこを塞ぐかということを記述するものである。
これらの形式は、単独で使われることもあったし、複合的に使用されたりもした。近代の記譜法の直接の先祖は、ネウマ譜になるのだが、他の記譜法の概念も、その中には、投影されているのである。そして、やはり、この概観だけからも、ほとんどの方法が、音高の表示のみによっていることに気付く。音高の表示は、早い段階になされたと先に述べたが、そもそも、楽器という器具が存在し、その扱い方で、異なる高さの音がでるのだから、明確な意識をもって、弁別しすることができる。では、それに対し、音価の記譜法の獲得は必ずしも後回しにならなければならないのかというとそうではない。ただ、西洋の近代の時間的構造を持つ音楽観から見れば、遅れたように見えるにすぎない。たいていの記譜法の歴史が語るほど、音価の獲得ができなかったわけではない。むしろ、する必要がなかったのだと私は考える。昔はなくて、今ある物をなにもかも発展、進化だと考えたくないのと同じことである。ここからは、西洋の記譜法の変遷をみていくわけだが、その前に、今、述べたことの一つの例として、かつて存在した、音高も音価も記述できた、ある記譜法をとりあげたい。これは、西洋以前という意味でも、重要であるし、音価のシステムについての考察にも有用な例といえよう。さらに、音楽理念的[注12]には、西洋のはじまりとも言える古代ギリシアの例である。
3.ギリシアの文字譜
もっとも早い段階に、音価の記述を体系化したのは、おそらくギリシアのベラーマンの無名者の理論書である。リズムの表示方法は、基本的な音価の2倍、3倍、4倍、5倍とそれぞれ記号によって示され、休止譜もいくつか存在した。ギリシアの楽譜は、リラ[注13]の奏法と関連した文字譜である。基本的な音高をあらわす文字とリラのポジション(というより、むしろ指)を示す二つの文字の組み合わせで表示される。したがって、タブラチュアの要素と一体化している例とも言える。この器楽譜とは別の、声楽譜という形態では、同様に三つの文字で音高を示すのだが、リズム記号は省略される。それは、おそらく、ギリシア語の特質によるのだろう。T.G.ゲオルギアーデスによれば、ギリシア人において、音楽と韻文 Vers は、ほぼ同時に存在するものであるとされる[注14]。言い替えれば、韻文とは言語であり、同時に音楽であった。これは、ギリシア語のムシケーという言葉に、よく表わされている。いまでは、音楽(ムジーク)の語源として語られているが、その言葉は、実際は、音楽と詩の一体化したまったく異なる事象を指した。つまり、そこにおいて、音楽と韻文は決して分解できず、韻文、つまり言葉のリズムは常に音楽のリズムを規定していたのである。他のヨーロッパ言語とは決定的に異なる長短リズム性 Quantitas rhythmik が、音楽的時間を、すでに内在していたとすれば、それは、あえて記録されなくとも、誰が歌っても同じリズムになるはずである。したがって、声楽譜には、リズムを表示する必要はない。
ところが、ゲオルギアーデスは、さらに、このようなギリシア語の性質が保たれていたのは古い時代に関してのことであるという。音楽的要素は、徐々に言語から離脱し始めた。紀元前4世紀ごろからその過程は開始され、紀元後2〜3世紀ごろには、韻文は、音楽的リズム性を完全に失い、音楽と散文 Prosa が残ったという。ゲオルギアーデスは、「根源的分離」と表現しているが、ここにおいて、声楽譜が音価の記述なしでは、再現できないという状況を生んだと考えられるのではないだろうか。一般的に、ギリシアの場合、器楽譜が先にでき、その影響で声楽譜ができたということになっているが、もしかすると、この韻律の崩壊が原因で、リズム体系を作らざるを得なくなったのかもしれない。少なくとも、器楽譜のリズム表示は、言語の助けを失った声楽譜にとって極めて有用に使われたであろう。トラレスで発見された紀元後1世紀ごろの碑文で、セイキロスが妻の死にあてた歌の楽譜には、リズムやアクセントを示す記号がそえられている。
このように、言語と歌により、音高と音価を厳密に規定することを重要としない音楽もある。では、近代五線譜法に見られる音価と音高への固執は、西洋近代の音楽に至る道筋の上に存在した、どのような理念や音楽様式によって要求されてきたのだろうか。その変遷について調べていこう。
第2章へ