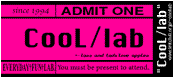"CooL/lab"-art review
『ネオ・ファンタジア』
『スーパーリアリズム--カメラの眼を超えて--』
『真贋のはざま デュシャンから遺伝子まで』
「20世紀版画の軌跡展」
東京都現代美術館
現代美術について
*新しい順です。
at 東京都写真美術館
 「カラフルなアニメとクラシック音楽の美しく華麗な融合」を期待していると、いきなり虚を突かれる。なんとも暗い雰囲気のモノクロの実写パートが始まるのだ。バケツと雑巾を手にオペラ劇場の床をふく少女(ヒロインか?)。数十人の薄汚れた老婆が、工場(?)から連れ出され、まるで収容所に向かうかのような荷車に乗せられる。オペラ劇場のような所に、進行役の身なりの良い男が現れ、「新しい着想を得た」と語りはじめる。それは、クラシックの名曲をアニメーションで表現しようという、実に「斬新な」思いつきだ。ところが電話がなる。ハリウッドのプリズニーだかなんだかという男がすでにそういう映画を作っているというのだ。この辺りからして笑いが込み上げる。しかし男はめげずに、オーケストラと指揮者と、アニメータを用意する。オーケストラは、さきほどの老婆たちだ。昔風の無気味な衣裳を来て、なんと古楽器(大昔の竪琴とか)を手に「ヌードは断った」とか「貞操は守ったとか」ゴシップを話している。指揮者はそうとうエキセントリックで暴力的な大柄の男。そしてアニメーターは、地下牢で壁に繋がれていた気弱で神経質そうな男というメンバー。このメンバーでのドタバタ劇(フェリーニ風と評されていた)を間に挟みながら6曲の作品が紹介される。演奏と解説がリアルタイムでアニメにつながる雰囲気は本家『ファンタジア』に合わせているが、いきなりゴリラが現れて指揮者を襲ったり、進行役が連れて来た売春婦とアニメーターがピアノの中で事に及んだりと(ピアノが使われる曲はない)、食事の時間と称して配給食のようなスープが出て来たりと、なんとも非ディズニー的である。ただ、そういったドタバタのやり取りの中から、アニメーターが次の曲の着想を得て、描いて行く過程は、音楽=アニメパートにすんなりとつながっている。 「カラフルなアニメとクラシック音楽の美しく華麗な融合」を期待していると、いきなり虚を突かれる。なんとも暗い雰囲気のモノクロの実写パートが始まるのだ。バケツと雑巾を手にオペラ劇場の床をふく少女(ヒロインか?)。数十人の薄汚れた老婆が、工場(?)から連れ出され、まるで収容所に向かうかのような荷車に乗せられる。オペラ劇場のような所に、進行役の身なりの良い男が現れ、「新しい着想を得た」と語りはじめる。それは、クラシックの名曲をアニメーションで表現しようという、実に「斬新な」思いつきだ。ところが電話がなる。ハリウッドのプリズニーだかなんだかという男がすでにそういう映画を作っているというのだ。この辺りからして笑いが込み上げる。しかし男はめげずに、オーケストラと指揮者と、アニメータを用意する。オーケストラは、さきほどの老婆たちだ。昔風の無気味な衣裳を来て、なんと古楽器(大昔の竪琴とか)を手に「ヌードは断った」とか「貞操は守ったとか」ゴシップを話している。指揮者はそうとうエキセントリックで暴力的な大柄の男。そしてアニメーターは、地下牢で壁に繋がれていた気弱で神経質そうな男というメンバー。このメンバーでのドタバタ劇(フェリーニ風と評されていた)を間に挟みながら6曲の作品が紹介される。演奏と解説がリアルタイムでアニメにつながる雰囲気は本家『ファンタジア』に合わせているが、いきなりゴリラが現れて指揮者を襲ったり、進行役が連れて来た売春婦とアニメーターがピアノの中で事に及んだりと(ピアノが使われる曲はない)、食事の時間と称して配給食のようなスープが出て来たりと、なんとも非ディズニー的である。ただ、そういったドタバタのやり取りの中から、アニメーターが次の曲の着想を得て、描いて行く過程は、音楽=アニメパートにすんなりとつながっている。
一曲目はドビュッシーの《牧神の午後のための前奏曲》老牧神がニンフに恋をする。ディズニー版(『ファンタジア』『ファンタジア2000』合わせて)がほとんど印象派の音楽を取り入れないのは、そのエロスを描けないからかもしれない。ギリシア神話が題材と言う点では『ファンタジア』の《田園》に似ているが、ここに登場するのは妖艶な全裸のニンフたち。老牧神は必死にアプローチするが、若く見せようと顔に塗った白粉がはがれたり、入れ歯がはずれたりし、ニンフに相手にされない。そういうストーリ−であるが、たくさんの女性の乳房だけでできた木や、沐浴するニンフなど、アニメーションも幻想的で官能的というよりエロい。
次はドヴォルザークの《スラブ舞曲第7番》マイナーな曲だ。古代の村。みんな壁に穴を掘って暮らしていた。一人の男が、荒野に家を建てた、すると残りの全員が同じく家を建てる。最初の男はおもしろくないので、今度は石で数階建ての家を建てる。しかし、また全員が真似をする。家はどんどん高くなる。最初の男が、ふと外に出て、気がくるったような踊りをしてみる。すると皆それを真似するではないか。自分をハンマーで殴れば、みんな殴る。彼は軍装し歩き始める。後ろには全員が彼を真似て行進しついて来る。そうして辿り着いたのは崖っぷち。崖の少し下に一人が掴まれるくらいの木が飛び出しているのが見えた。悪意が閃く。男は崖から足を踏み出し落ちたと見せかけその木に掴まる。その時、彼が見た物は??アニメ的な単調な繰り返しの映像が大衆心理をシニカルに描いている。これも非ディズニーで愉快だ。
進行役の男が指揮者に尋ねる。
「次の曲は?」
「ラヴェルのボレロ」と指揮者が答える。
「ラヴェルのボレロですね、有名な曲だ。で、それは誰が作ったのですか」
「・・・ラヴェルだよ」
というわけで、僕の最も敬愛する作曲家ラヴェルの登場だ。なぜディズニーが取り上げないのか不思議なくらい。この作品は多分、この『ネオ・ファンタジア』の最高傑作、執拗に繰り返されながら徐々に拡大していく《ボレロ》。始まりはある惑星。宇宙船から投げ捨てられた一本のコカコーラの瓶。その瓶の中でコーラの泡が徐々に動きだして・・・。ここで描かれるのは進化の物語。最終的に恐竜(のような生き物)が大群で行進するさまなども含め、これは『ファンタジア』の《春の祭典》へのレスポンス作品と思われる。しかしこの恐竜(のような生き物)の陰にはいつも邪悪な目をした猿(のような生き物)が徘徊している。やがて大行進の末に恐竜(のような生き物)の眼前に表れる異様な光景。そして人間の姿の巨像が割れた中には、あの邪悪な猿が。《ボレロ》は音楽的には同じメロディの繰り返し、だからこそ、アニメーションで語られるテーマが肉迫して来る。息を飲む大傑作だが、音楽上のオチがアニメーションのオチに一致していないのが少し残念(音楽終了後に、アニメだけでオチが来る)。『ファンタジア』の《くるみ割り人形》でも、最後のオチがストコフスキーというがっかりモノだった・・・。
この作品のマスコットキャラ(?)の愛くるしいネコが登場するのがシベリウスの《悲しみのワルツ》。今まで、毒々しく、諧謔的で、猥雑な物を見せておいて、ここでいきなり泣ける話が来るのがすごい。廃虚と化した建物(ほとんど壁の部分しかない)に、一匹のネコが住んでいる。そしてそこで昔繰り広げられた美しい日々を回想する。これは絵画的な背景美術も素晴らしいし、ネコの表情や動きなども相当緻密に描かれていてすごい。壁(平面)が一気に前に迫り出し、かつての部屋(立体)にメタモルフォーゼするシークエンスなど、結構、現代性がある。実写映像の取り入れ方も、逆に新しい気すらする。そしてとにかく切ない。大友克洋の『MEMORIES』の中の一作「彼女の思いで」などにつながっているような気がする。
この曲が終わると、オーケストラの老婆たちは、涙しながら、鼻水をすすり、そのちり紙を、薔薇のようにアニメーターに投げる。しかし指揮者はおもしろくない。暗い話ばかりだ!と憤懣やるかたない。そこで、先程の売春婦が登場しアニメーターのテンション(?)をあげる。
ヴィヴァルディの《ヴァイオリン協奏曲ハ長調》に載って創作されるのは、ミツバチの食事風景。ところがそこに人間のカップルが現れて、いちゃつき始め、ミツバチの食事を台無しに、という話だが、完全なセルアニメのように描かれるミツバチと、スタイリッシュに描かれる人間の描写、またミツバチの視点から見た、カップルの大きさが面白い。人目(ミツバチ目)も気にせずキスをし、抱き合って転がり回る。これは確かに邪魔かも。
さて、最後を飾るのはストラヴィンスキーの《火の鳥》(あの進行役にはドストエフスキーの、と紹介される)。ディズニーが2000年に製作した『ファンタジア2000』の最後を飾った曲でもある。まずクレイアニメから始まる。作られるのは、何らかの生き物。試行錯誤の末、できたのがアダム、そしてイヴ。ここでアニメに移行し、一匹の蛇が二人にあの実を食べさせようとするが、二人は断ってどこかへ行ってしまう。しかたなく、その実を自分で食べた蛇が見た物は。大都会、セックス産業、バイオレンス、文明社会の悪しき物のオンパレ−ド。さらに実写とのコラージュがこの雑雑しさを盛り上げる。最後まで、批判精神というか、人間への嘲笑を忘れない。ディズニー版で、これだけの批判精神を見い出すとしたら、せいぜい《魔法使いの弟子》における大量生産の暴走くらいか。ちなみにこの時すでに暴力的な指揮者は猿にやられているので、演奏は蓄音機に任されている。
そして、さあ、フィナーレという所で、アニメーターがあの雑用係の少女をお姫さまに変身させ、自分を王子様に書きかえ、空を飛んで逃亡してしまう。困った進行役は・・・。と最後までドタバタで、納得の行く解決感が全くない。すべてがごちゃまぜで、騒がしい。しかし、そこがものすごく楽しい。『ファンタジア』とばかり比べるのもおかしいとは思うが、アニメ−ション技術だってすごい!こんな作品が今まで、埋没していたと思うと本当にもったいない。音楽だってカラヤン=ベルリンフィルだし(だからどうとうい訳ではないが)、これは『ファンタジア』という表現形態に、また別の魅力を与えたという点で、とても偉大な作品だと思う。(しかし一方で、『ファンタジア』がこの作品の36年前だと思うと、やはり『ファンタジア』は異常)
ウォルト・ディズニーは、1966年12月15日に亡くなっているので、この作品を目にする事はなかったはずだが、ファンタジアの構想は、元々曲を入れ替えながら、継続的に発表するという物だったので、もし、彼がこの作品を見ていたら、きっと、発奮して、新しい『ファンタジア』を作っただろう。そうすれば、『ファンタジア2000』まで、60年もの歳月が流れなくて済んだのに。そして、この『ファンタジア』という表現形態は手塚治虫なども挑戦しているし、現代の(また、これからの)アニメーターたちも、たまにやったらいいのに、と思った。(2005/1/25) →『ネオ・ファンタジア』のホームページ
|
↑ページのトップへ↑
at いわき市立美術館
久しぶりのレビューです。最近美術館から疎遠でした。というわけで、福島県いわき市のいわき市立美術館に行って来ました。いわき市立美術館は、公立の美術館なのに、国内外の戦後の現代美術をコレクションするというある意味胆力のある美術館です。アレシンスキー、クライン、アペル、フォンタナ、金昌烈、ステラ、トゥオンブリー、ボイスなどなど錚々たる顔ぶれです。
今回は、そのいわき市立美術館で開催中の『スーパーリアリズム--カメラの眼を超えて--』という、いわゆるアメリカン・フォトリアリズムの展覧会を観にいわきに行って来ました。現代美術においては、具象絵画というのは、あまり描かれて来ませんでした。物の姿を写実的に書き写す事に意味がないというのが、まあ、印象派以降(?)現代美術の発想の根源にあるわけです。だから「静物」とか言って、花瓶とか果物をそっくりに書くような絵画は古い物になっていました。で、1960年代以降、アメリカで誕生したのが、スーパーリアリズム絵画です。これは、つまり写真と見紛う程リアルに描く絵画の事です。観たままをリアルに、ではなく、写真に取られた光景を写真のままにリアルに、です。ほら、すでにリアルの概念にさざ波が立って来て、「現代美術的に」おもしろいです。
例えばチャールズ・ベルの『ビー玉5』。キャンバスに油彩で、鏡のような地面に置かれた7つのビー玉が描かれています。はっきりいって、相当キャンバスに接近して、キャンバスの素地や筆触が見えてはじめて、「あ、絵だ」と分かるのです。この展覧会には67点もの、このような作品が展示されていますが、大部分が、何らかの形で光の反射を取り入れた物です。このビー玉やバイクや車などのメタリックな部分、ショーウインドウ、雨粒、銀食器、水面・・・。ここで1つの事実が浮かび上がります。普通の絵でもそうですが、反射も光もすべて目の錯覚です。額縁が光っているのは、本当の反射ですが、絵の中の光は所詮、絵の具の集まりです。とりわけ、反射と光を描く事によって、スーパーリアリズムの絵画は、その点に目を向けるチャンスを与えてくれます。そして、網膜に焼き付く像も仮象かも、なんて話しにまで、思考は飛躍していきます。
さらに、もう一つの事実ですが、現実上、我々は、広い範囲をいっぺんに観る事は出来ません。何かに必ず「焦点」があって、他はぼけてしまいます。カメラで撮った写真も同様です。例えば、リチャード・エステスやアンソニー・ブルネッリの風景画は写真のように見えるのですが、しばらく観ていると、何か、違和感を感じます。写真のように、その街角に立ったら見える物であるはずなのに、現実の視野とはどうも違うのです(これは、しばらく観ていないと気が付かない程の微妙な差なのですが)。つまり、全ての物にピントがあっているのです。右も左も近くも遠くも。この視野は新鮮です。きっと我々は、風景を見る時、焦点をどんどん動かして、全体にあった像を頭の中で結合させるのでしょうが、写真ではそれは不可能です。肉眼だってパッと見には無理です。したがってこれらの絵画は、現実そのものではなく、頭の中のスーパーリアルなのです。リアルを突き詰めて、虚像になっていく面白さが目の前に開かれているわけですね。
逆に、写真のようにピンボケの部分を精密に描写する画家もいます。この場合、そのボケた部分を描くテクニックは強烈です。ボケていると認識して、ボケている事を観察し、ボケているように書くというのは、ちゃんと見える物を書くのとは違う気がします。絵書きではないので、わかりませんが。
どの画家の絵も、よくよく近付いて観察すれば、写真ではなく絵だということがわかります。ただ、僕の目にはどうしても分からなかったのがドン・エディの絵画です。どんなに凝視しても、絵なのか写真なのか分からない程のテクニックには驚かされます。これまで、あまり興味を持たなかったのですが、画材や絵の具の種類などについても興味が湧いて来ました。
いずれにせよ、写真を絵におこすという事を考えると、複製時代の芸術という、いつもの論議も思い出させる一方、イメージとはなんなのか、という哲学的な問題も考察できて面白いと思います。そうして、僕は、今、この展覧会のパンフレットという形で、写真を絵におこしたスーパーリアリズムの絵画のカタログとしての写真を見ているわけです・・・。
スーパーリアリズムに興味のある方は、いわき市立美術館にて7/4まで開催してますので行ってみて下さい。67点という数からして足を運ぶ価値ありです。その際は、温泉や海の幸なども是非(僕はいわき湯本の温泉宿に1泊しました)。(2004/6/9) →『スーパーリアリズム--カメラの眼を超えて--』
|
↑ページのトップへ↑
at 東京大学総合研究博物館
|
SPEAKER370の脚本執筆の参考に、「なかなか良いんじゃない?」と思われる展覧会があった。東京大学総合研究博物館の企画展『真贋のはざま デュシャンから遺伝子まで』である。
まず、入り口に、デュシャンの大ガラスがある。それだけでも、ぞっとする美術展だ。11月29日の金曜日は、晴れて、東大の構内は、銀杏の絨毯。一面、金色に輝く絶景だった。この展覧会は、なんと言っても、我が家から徒歩で行けるし、入場無料と聞いていかないわけにはいかない。この企画展の意図は、現在のオリジナルとコピー関係を捕捉することにあるようだ。現代はコピー文化と言われて久しい、何もベンヤミンの『複製技術時代の芸術作品』を持ち出さなくても、現在は、複製技術時代である。そして、何も、それは嘆かれたり、反省を求められたりするようなものでは無い。むしろ、オリジナルとは何か?と問う所にこの展覧会の眼目はあるようだ。
展覧会は、美術に留まらない。頼朝像の教育用デジタル複写物、中国古代の竹簡の偽物(焼き鳥の竹串同然の材質と判明した)、ゴーギャンの贋作、美術上の模写、紙幣、切手、レプリカ、原子構造の反復からなる化学模型、人体模型、鉱物モデル、フランスの美術雑誌の表紙デザインをそのまま流用した日本の雑誌、発掘品の捏造、古い複製技術である版画、肖像画の代わりとなった写真、昆虫の擬態標本、なぜか、男性器の張り型(でかい!)。和紙に書かれた絵を2枚に剥ぐ「あい剥ぎ」の技法等は、どちらが、オリジナルでどちらがコピーとも言えない。
例えば、ラファエロの銅版画がある。これは、もちろん原画があって、その原画を広く普及させるために作られた。しかし、この銅版画は、コピーとして芸術的価値が取り払われる訳では無い。むしろ、この銅版画の写真があることで、銅版画は写真のオリジナルになる。オリジナルとコピーの対立図式は、もはや当て嵌まらない。世の中には、偽札と言う物がある。フェイクの紙幣だ。しかし紙幣のオリジナルは、私たちが手にしている物だろうか?あれは、印刷物に過ぎず、その印刷物を「本物」だとする共通了解のもと、私たちは紙幣を使う。コピーする権利の広がりと、国ないし、独裁者の権力範囲は重なると言う考察も興味深い。オリジナルとコピーは無限の連鎖なのだろうか?
また、最近のショッピング・モールやテーマ・パーク内には、「〜風の町並みを再現した」フェイク・タウンが溢れかえっている。こうして、現実体験は、コピーにより疑似体験に進む(批判しているわけではないです)。そして、現在の技術は、コピーとオリジナルの差異をなくしてしまった。ネット上では、同一のコンテンツが一点の差もなく、無限に永遠に繰り返される。『コントローラー370』(SPEAKER370の上演作品)でも取り上げたが、「エターナルなコピー&ペースト」だ。今後、バイオ技術が可能にする物は、さらに、同一の遺伝子体、クローンである。法制化が進む中で、ことはSFではなく、にわかに現実味を帯びている。クローンは、本体のコピーでない、という。それはそれで、オリジナルなのだ。
展覧会は、一応、美術作品を掛け橋に、いろいろな実際上の道具(男性器の張り型はなんだ??)に及ぶが、さらに、現在の科学技術のコピー性能について、学びたい予感を残した。
一つのベクトルとして、現実体験が、疑似体験に、そして、仮想体験に向かう図式があるが、私たちのオリジナリティが、まさに、「真贋のはざま」に飲み込まれていくようで、しかも、知的にスリリングな展覧会であった。こうして、いろいろな実例を目で観て考えると、おもしろい事はたくさんある。こうして、書いていても、考えは、漠としてまとまらないが(それを読まされる方々には申し訳ないです)、とにかく、オリジナルを観て、オリジナルを考えるのではなく、コピーからオリジナルの意味を(どういう意味を持っているのか?あるいは、そもそも意味なんてないのか?)考えるきっかけを作れる好意的な(ちょっと皮肉のきいた)展覧会だった。最近、次回の脚本(volume.08『F.L.O.O.D.』の事)のために、「脳」の勉強をしている。脳の構造等を観ていても思う。自分のオリジナルは、どこにあるのだろうか?
同展覧会は、12月9日まで(東京大学本郷キャンパス、東京大学総合研究博物館)。デュシャンの大ガラス『彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも』は、破損を防ぐため普段は、滅多に運ばれる事がありません(確か、いつもは駒場キャンパスにあるはず)。レプリカですが、デュシャンの合意のもと、再制作された物なので(だからオリジナルなのか?コピーなのか?)それを見るだけでも、価値ありです。お暇な人は是非。
|
↑ページのトップへ↑
at 安田火災東郷清児美術館
丸井では、近現代の作家のコレクション、特に版画作品を収集しているらしいのだが、もったいないことに、このコレクションは、一般公開される機会がほとんどなかったそうだ。版画というとあまりピンと来ないし、知っている作品が少ないと思うかもしれないが、リトグラフや、エッチング、アクアティントという言葉を美術館等で目にする機会は多いと思う。リトグラフは石版画(亜鉛板も使う)だし、エッチングやアクアティントは、銅版画の技法の一つである。さらに、印刷技法という意味では、これにスクリーンプリントも加わるので、現代の代表的な画家たちの重要な作品が入って来る。
まさに、この展覧会は、現代を代表するスーパースターたちが一同に介したという印象だった。まず、ロートレック、ボナール、ムンク、ピカソらの作品で、20世紀への目の準備をする。前回の反省もあるので、少し、足早に、レジェ、ブラック、ルオーらの作品が並び、ここからマティスの目白押しになる。それも、デクッパージュ(切り絵)。マティスは、後年、体力的に絵筆を握る事がままならなくなり、その色彩表現を昇華させる為に、見事な手法を使った。それが、切り絵だ。こうして連作<ジャズ>が生まれた。ここでは、<ジャズ>シリーズ全20点が所狭しと壁に並び、マティスのあまりにも苛烈な色彩が僕を圧倒した(この描写はいかにもだなぁ・・・)。エッシャーの田園と鳥が入れ違いながら、昼夜を分かつ<昼と夜>は有名だ。この作品は、木版になる。また、ミロのエッチングもいくつか展示されており、奇妙な単細胞生物のような線が、いかにも可愛らしかった。同じようにデュビュッフェの<にんじん鼻>はとても観たかった作品で、あまりの愛らしさに、盗みたくなる。美術館にとって(というか全ての人にとって)泥棒は許しがたい存在だけど、美術館に足を踏み入れた時、自分がキャッツアイだったら、どの絵を盗むかと考えるのも一興だと思う(金になるならないではなくてネ)。あとの有名ところは、カンディンスキー、クレー、シャガールなどだが、ここまででも凄いのに、これからが良いんだなぁ。つまり、僕が最近現代美術の本でお目にかかった名前が次々と登場する。まあ、それを馬鹿みたいに列挙してもしょうがないので、印象的な作品を書いて行こう。サム・フランシスの<憂鬱(赤)>は、幅2メートルに及ぶ、大きなリトグラフだ。ドリッピングのように、絵の具が垂らされたり、流されたりしている抽象的な作品だが、この赤や黄色、橙で構成された絵の具の染みは、概ね画面の輪郭に沿ってたらされており、画面中央には大きな余白(空白の部分)がある。この作品の前に立つと、その空間に視点が凝縮されて、画面がぼやけて来る。すると、ふいに回りの色彩が自分を包み込んで、その白い部分に溶け込ませようとしているような感覚がするのだ。まさに「空」という感じ。フランク・ステラの作品も観てみたかった。<ペルシアの星>は、シェイプト・キャンバス(支持体、この場合キャンバス自体を変型させる)の作品だ。この作品では、文字どおり星(いや、雪の結晶)のような形をしている。幾何学的一連のパターンの繰り返しがステラの十八番だと思っていたら、<パシフィック>、<ハイデルベルグの大樽>に驚かされた。このコラ−ジュ作品は絵画というより、彫刻だ。ダンボールや、金属に色彩を施して、コラージュとする。しかも高さが2メートル弱はあり、その重量感はすごい。思わず、口を開いて見上げてしまう(しかし作品としてはあまり好きではなかった)。ラウシェンバーグやジャスパー・ジョーンズの作品に登場する意味のありそうなモチーフ。雑誌の切り抜きとか、写真、日用品や引用。こういった作品は、やはりその物の意味性、無意味性に(その罠に)囚われていくのがおもしろい。ジャスパー・ジョーンズの<デコイ>では、画面にGREEN、VIOLET、RED、ORANGE、YELLOWの文字が隠されながら書かれているが、それらは、黒や、灰色、水色等で書かれており、画面も禁欲的にモノトーンだ。エドワード・ルッシェの<Western>を思い出す。
ポップ・アートのスタートだ。クレス・オルデンバーグのおばけプラグ<Three-way Plug Scale B, Soft>を前に取り上げたが、ここでは<ティーバッグ>だ。紅茶の液体そのものごと巨大化されたティーバッグが、真空パックのようにビニールに閉じ込められて、壁にかかっている。これほど、ティーバッグをじっと観る事があるだろうか。手で持つ部分、ティーバッグとの接点である糸、ティーバッグの形、しみ出して来る茶色い紅茶のしみ。そしてまたおもしろい事に、この作品の見た目は、テーブルなどの上に無造作に置かれたティーバッグで、しみも辺りに飛び散っている。しかし画面は垂直に立ててある。本当なら、液体は、滴り落ちるべきなのだが、そのまま、パッキングされている。水平のままの姿を垂直にすることに注目するのもおもしろい。
ここで、コーナーはリキテンシュタインとウォーホルに突入する。丸井コレクションの中核を成すのだろうか、相当数ある。リキテンシュタインは印刷物特有のベンデイ・ドット(網点)で画面を構成する。漫画の一コマを拡大した時、いままで色の代用だった網点があらたなデザインを生む。オルデンバーグを観た後では、拡大という作業から現代美術を眺めるのもおもしろそうだ。それは、つまり物の価値の転化なのだろう(わかんないけど)。しかしリキテンシュタインの漫画の作品の金髪の部分(黄色と黒)だけを観ていると、相当、抽象絵画としても凄いと思う。
エドワード・ルシャの<スタンダード・ステーション>は、実在の(?)ガソリンスタンドのイラストのように単純化された色と、写真のようにリアルな描写が見た目の印象だが、何より、看板に大きな文字で書かれた「STANDARD」の文字が実に脅迫的だ。ややポップなイラストレーションのような画面を上部から押さえ付ける「STANDARD」の文字。覚醒剤などを吸って、このガソリンスタンドを観たら、この「STANDARD」の文字は、どんな命辞となって襲って来るのだろうか?作品とは関係ないだろうが、街に溢れる文字は少しずつ、僕らの感覚を洗脳しているような不安にすらかられる。
よく、二つの同様の絵の構図を少し変えた物を並べて、どちらの構図が良いかといったような宣伝がある。構図は伝統絵画の最も重要な問題なのかもしれない。その目で、アレックス・カッツの人物画を見ると、ほくそ笑みたくなる。<赤いコート>では、あまりにも拡大されたアップの顔は、画面からはみ出している。女性の左目と唇は画面の左端で途切れてしまう。かっこいいではないか。この女は本当に存在して、目の前で、自分をやや上から覗き込んでいるように見える。映画の画面構成といえば、わかりやすいかもしれない。
続いて、やはりコレクションの中核なのかホックニーの作品も多い。<ウェザーシリーズ>はカレンダーにはもってこいだ(失礼かな)。浮世絵の天候表現が用いられている。特に最後の「風」の絵で今までの絵が吹き飛ばされているのは笑える。ここには、ある種の穿った前衛精神もなく、感じられるとすれば、笑って聞き流せるような軽い皮肉程度だろう。
ロバート・ロンゴの<メン・イン・シティーズ>も素晴らしい作品だ。ウイリアム・ギブソンの『記憶屋ジョニー』を映画化した『JM』(キアヌ・リーブスやビートたけしが出ていた)の監督ロバート・ロンゴと同姓同名だが、実は同じ人物である(意味が分からない文だ)。正装をした男女が、背景のない画面の中で、不可解なポーズをとっている。踊っているようでもあるし、強風に耐えているようでもあるし、また、倒れようという瞬間にも見える。解説には、モデルに向かってボ−ルを投げたり、ロープでひっぱったりした瞬間を写真に捉え、それを描いている。喜怒哀楽の銅の感情でも無く、威厳に満ちた立ち姿では無く、また男を誘う裸婦のしぐさでもない。モデルにある意味を仮託しないし、モデルを使って絵画にある意味を付与しない。ただ、読みとる事の出来ない人物像がそこにはある。せいぜい、現代社会での正装という物の持つ感情のなさ、ニュートラルな冷たさを感じとる事が精一杯だろうか。かっこいい作品だが、クールと言ってしまうだけではもったいない。
もっとも最後の壁に、エピローグのように書けられたキーズ・ヘリングの<自由の女神>をもって、36人の作家による105点の展覧会が終了した。版画だけに絞っても十分圧巻と言える展覧会であったような気がする。できる事なら、一般公開の機会をまた持っていただきたい。僕の訪れた日は、会場は、熟年層と大学生にしっかり、分かれていたが、もっとより多くの人に見てもらいたいエンターテイメント性が十分に会ったと思う。蛇足だけど、この展覧会のいわゆるカタログは廉価で、しかも箱入りで、相当良いと思った。(1997/9/18)
|
↑ページのトップへ↑
東京都現代美術館ができる前、新木場のあの公園(都立木場公園)は、馬鹿みたいな公園だったような記憶が、小さい頃の風景画のような記憶としてある。その地に1995年東京都現代美術館はオープンした。まわりに何も無いので、現代美術館らしい都会的な雰囲気の全くない美術館で、また上野と違って自然的環境もそれ程優れていないので、相当、周囲の環境に溶け込んではいない。はっきり言えば、悪目立ちをしている。大江戸線画でき、地下鉄3線の最寄り駅を持つが、まったく最寄りではない。不運な事に、この日、東京にはひどい大雪が振り、僕は遭難するかと思った程である(それは言い過ぎ)。
さて、美術館に行くと、当然、美術作品と向き合う事になりますが、その向き合う作品の量はどれくらいあるか知っているだろうか?いかにも知っているような書き方をしたけど、僕は知りません。ただ、「多い」という事は分かる。それなりの美術館に行けば、100点以上の作品を、1日に、いえ、数時間のうちに鑑賞する事になり、直接くらべる事なんてできないが、例えば、音楽の作品を鑑賞しようと思ったら、1時間弱の交響曲で、100時間(ぶっとおしで4日以上です)になる。
いかにも、頭の悪いたとえをしてしまって、後悔しているが、話を先に進めよう。東京都現代美術館の場合、所蔵作品はパンフレットによると平面作品3、200、立体作品300で、計3、500点です(今は、3、600〜3、800ぐらいらしい)。その中から、100〜200点くらいが常設展示されているわけだが、これを一日で見る事はできても、作品として消化する事は不可能だ。また、この美術館のように所蔵が多い場合、展示替えが行われるが、都現代美術館は、確か年4回くらいの早いペースで入れ替えがあり、当然、観たい作品がお休みをしている事もままある。僕の場合、たいてい、はずれてしまう。この大雪の日も、狙っている作品にはほとんどお目にかかれなかった。
都現代美術館の気の効いている所は、各展示室の展示作品に関するポストカードサイズの解説がおいてある所だ。それを手にして読んでみるのも良いのだが、目に止まった「おもしろいな」と思った作品のそれを持って帰って置くと、あとあと、どの作品に興味を持ったかを明確に知る事ができる。そして、そこから、レファレンスを拡大していく事ができるわけだ。
この日目に止まった作品は(カードが品切れになっている物もあるのだが)、まず、エドワード・ルッシェの<Western>である。そういえば、ここでは作品のタイトルは原題を書いたが、題名が邦訳されている物は注意が必要だ。題名をあまり参照するな、などと言ったが、題名も作品の一部である以上、精密に観測したい。詩的であれ、記号的であれ、この言葉にも意味は込められているのだから(ただ、その意味から自由になって良いと言ったわけである)。あなたが、青いテーブルか何か堅い素材のものの上に、小さな水たまりを作ったとしよう。そして、その水たまりに指をつけ、さっと文字を走り書きする。「Western」と。トロンプ・ルイユ(だまし絵)という絵があるが、ようは本物、あるいは平面なので写真と見まがう程のリアルさで描かれている。だが、この画面の中に、ウェスタン(西洋、西部)な要素は見出せない。まるで、喫茶店で、友人と気のない話をしながら、コップの結露からテーブルに広がった水で、無意識に書いた字のようだ。自動筆記といおうか。意味も無く、ふいに「Western」と。
さてさて、現代美術のおもしろさはここにある。花の絵を観て「きれいな花だなあ」、裸婦像を観て「美しい肉感だ」というのとは違う。この絵には、何を見れば良いのかが、明確に示されていないのだ。どうおもしろがれば良いのかが、わからないから、「おもしろくない」のである。その「おもしろくなさ」に気分を害すようなら、「分かりやすく」「おもしろく」「作られた」何か別の物を観ればよい。この絵を前にはっきりと分かる事は「水で書かれたWesternの文字」、「リアル」だなと言う事や「きれいなブルーだな」という事。もちろん、それを面白がる事はまず大切。大前提だ。そして、「意味不明」である事が「おもしろさ」を生む。なぜなら、「分からない」物は、必死で「分かろうと」するからである。そして、回答は人それぞれ。僕は、絵の中に書かれる文字に注目する事にした。「Western」の意味ではなく、「絵」なのに、書かれているのが「文字」として読めるということに。「Western」という言葉には当然意味がある。だが、この描かれた文字は、絵なので、意味は無い。結局、そこら辺までしか、考えを進められなかったが、文字、絵、記号といった、意味伝達の手段を扱っていて、しかも、この意味を伴う事の出来ない文字は、象徴的なのだろうか、やがて蒸発してしまうであろう水によってかかれている。そうでなくても、「Western」を構成する文字の水たまりは互いに接触して今にも、くっつきあいながら、姿を代え、文字では無く、水の映像になってしまいそうだ。ここらへんに、なにか、「おもしろさ」の元がありそうな気配を感じ取った。
この調子で書いて行くと、相当膨大な量になってしまうなぁ。と思いながら、次へ行く。クレス・オルデンバーグの<Three-way Plug Scale B, Soft>、壁に作者と作品名を書いたパネルが貼ってある。しかしその側に作品はない。もしかしたら、作品が無い事がこの作品なのか?疑問に思う。しかし、プレートには、「皮革、木」と材料が書かれている。なにか、メンテナンスで額を外してあるのかなと、やむなく得心して展示室を出る。しかしな、と思い振り返ると、作品はあった。天井からぶらさがる奇妙な形の大きな物体。作者の狙った効果か否か、美術館の目の高さに据えられた絵画を凝視する事に慣れた目には、それこそ驚愕のカウンターパンチだった。僕の注意力がなかっただけだが、これ程、印象的に作品に登場された事はない。茶色い皮の袋が大きく膨らんでいる。その先端、地面に向かって、木の棒が2本突き出している。木の棒の先端には、円い穴がそれぞれ開いている。と、説明風に眺めて行かなくても、すぐにわかる。天井からぶら下がっていた物は、巨大な電気プラグだ。これは、作者の「柔らかい彫刻」のシリーズだそうだが、パッと見、ちょうど、電気プラグ型のぬいぐるみと言えなくもない。確かに、本来プラスチックと鉄でできているはずのプラグが、皮革と木でできているのだから、工業製品と言う気はしない。見慣れた形の電気プラグが全く別の物に思えて来る。皮で出来たプラグの本体部(指で持つ所)はしぼみかけた風船のように、中身が無く頼り無い印象だ。宙ずりにされた頼り無い巨大な電気プラグ(型の何か)。これも<Western>と同じように、電気プラグの意味が不明になっている。一定の効果を狙っているんだとしたら、異化されているわけだ。あるいは、デフォルメだろうか。電気プラグは電気を媒介する物だが、このおばけプラグは、何を媒介する物なのだろう??分からないながらも、出合いの感動もあり、この作品は「おもしろい」。そして、「柔らかい彫刻」という言葉も、考えてみれば、独創的だ。何故、彫刻作品は堅かったのだろう。柔らかいはずの人体や、衣服のひだを巧みに堅い石で表現してきたのだ。堅い物を柔らかい物で表現しようと、誰も思わなかったのだろうか。
ああ、本当にきりがないので、後の作品で、印象に残った物は、列挙にとどめよう。蛇足かも知れないが・・・。
ジェームス・ローゼンクイストの<For Bandini>、デヴィッド・ホックニーの<A Lawn Sprinkler>、多田美波<周波数37306505>。ちなみに、この日は、ドナルド・ジャッドの巨大なミニマル・アート<無題 No.306>が目的でいったのだが、がらがらの展示室内で(大丈夫なのか、都の財政は?)ゆっくり堪能する事が出来た。
|
↑ページのトップへ↑
「現代美術は、おもしろいかどうか」というと、ちょっと、問題がある。逆に言えば、おもしろくない物というのは、実は珍しいし、それがあったとしても、それをおもしろいと言う人は必ず存在する。我々が普段、考えもしない、「ほこり」とか、その辺の砂だってきっと、内実はおもしろい。
現代美術は、おもしろい、事に間違いはないと思うけど、何が、おもしろいのか?所詮、「お前がおもしろいという、そのおもしろさが分からないんだよ」と非難される程度の個人的おもしろさかもしれない。だが、現代美術は、基本的に、おもしろくあろうとして作られている。おもしろかれ!と思って造られているのだから、やっぱりおもしろいのである。
ある人が「あの映画おもしろかったよね」と言った時、同意して「おもしろかった」というのは、表現としてややおかしい。言わずもがなだが、お互いのこの発言の力点が、はっきりしていないからだ。どこがおもしろかったのか。これを語る事に躊躇するタイプの人がいる。「おもしろい」とか「かっこいい」という形容詞は、固有の存在、もっと言えば、固有名詞意外に使ってはいけない。それは、話を漠然とさせる効果しかない。「あの映画」は映画名という固有名詞に置き換えられるが、それでも、発言の真価は問えない。映画は、何かを投影した物で、重要なのは、投影された物か、そうでなければ、投影の手法、またはそれらの組み合わせ方(組み合わせではなく、組み合わせ方)である。
話はとんでもない所に脱線してしまった。全ての(現代に限らず)美術作品は、絵が美しかったり、おもしろいのではない。我々の鑑賞は、描かれている物・形、描かれ方にあるのであって、その後に、付加価値について感想を持つ事ができる。作者はどんな人物であり、どんな主義を持っていたか、当時その絵がどう受け止められたか、その絵の成立にどんな物語があるか。他の作品と比較してどうか。(もっとも最後に)作者はその作品について何を語っているか。
また、誤解をされやすい事だが、芸術作品の見方は、作者がその作品を、どう捉えていたかとは完全に断絶される。作品の前面にいるのは、作品の背後にいるのも、鑑賞者である。ある現代美術作品を始めて観る時、特に気をつける事。
1.そのものを知らない事
2.まっ先に題名を見ない事
3.作品そのもの以外からの情報で最初の印象をつくらない事
である。
美術館で誤りがちなのは、知る事と観る事の勘違いである。その作品がウォーホルの『マリリン』である事を知るのと、その作品を観るのとは基本的に違う。我々は、知っている(と思っている)もの程、追求しない。美術館で、ウォーホルの『マリリン』の前に立った時、最初の感想は「あ、この絵は知っているぞ」であろう。いろんな本や写真で観た事がある。本物はここにあるのか(まあ、この場合、そこらじゅうにあるのだが)。へー。以上である(それは言い過ぎかな)。また、この場合、『マリリン』をじっと、芸術作品として観る事をウォーホルが望んでいたか、いないかも関係はない。僕は以前、東京都現代美術館のリキテンシュタインの『ヘアリボンの少女』の前を素通りした事がある。その時は、いろんな考えで、そうしたのだろうが、結局、今にして思えば、僕はその絵を知っていて、知っているから観なかったのだ。また、知っている物は単純に思える。はっきり言えば、僕らが何かを「知っている」という言葉は、「誤解している」という言葉と同義語だ。
題名も要注意だ。現代美術の作品のタイトルはそれ自体が独創的でおもしろい。ほとんど、作品の持っているイメージを転倒させるような物もあるが、ある程度、意味を持ってしまう物もある。言葉と言う物は、物が先に存在して、名前が付与されるのではない。言葉が、物を造る。物体をイメージ化するのだ。真っ赤に塗られたキャンバスをただ観た時と、その作品名が『血』である事を知った時とでは、赤に付与されるイメージが変わる。いや、むしろ、赤い絵を観て「赤い」と思った瞬間に、僕らは「赤」という言葉のイメ−ジの供物となってしまう。その事も無論、創造的に利用されはするが。ありていに言えば、一人の人物が描かれていて、その題名が『キリスト』であれば、もうその作品の見方は決まってしまうのだ。なんとなく、地面においてある木箱は、ただの木箱であるからこそ、様々な感想を抱く事ができる。が、「椅子」と書いてあれば、それは座る以外の何ものでもないのだ。
とにかく、まずは作品そのもの。後に情報である。また、題名を予想したり、どうやって書いたのかを推理する。例えば、色が重なりあっている時、どの色が一番下で、どの順に塗られたかを想像するのは結構楽しい。
さて、現代美術を僕がどう定義するか。現代とはいつか?一般的な定義は、
1:20世紀以降の美術
2:戦後(1945年以降)の美術
1の20世紀ということになれば、ピカソ、セザンヌ、マティス、シャガール、モネといったビッグネ−ムが並ぶ。
2の戦後となると、ポロック、デ・クーニング、ラウシェンバーグ、ロスコ、ウォーホル、リキテンシュタイン、フォンタナといった名前で始まることになる。
現在の僕の立っている場所からすると、2の方が、ピンと来る。やはり、セザンヌやモネは、古典的大家という様相をすでに帯びている。もっと現代美術に慣れ親しんでいている方なら、2で並べた名前も、すでにクラシックなのかもしれない。というわけで、2を採択する。現代美術より、おしゃれで、新しい感じのするモダン・アートという言葉もあるが、これは突き詰めても、水掛け論であろう。
まあ、そこはプロの美術史家や開催者の目を完全に信じて、「現代」とつく美術館、もしくは、美術展に「現代」という言葉が冠されている展覧会に行ってみよう。
|
↑ページのトップへ↑
 ガイドページへ戻る
ガイドページへ戻る
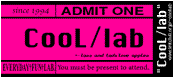
 「カラフルなアニメとクラシック音楽の美しく華麗な融合」を期待していると、いきなり虚を突かれる。なんとも暗い雰囲気のモノクロの実写パートが始まるのだ。バケツと雑巾を手にオペラ劇場の床をふく少女(ヒロインか?)。数十人の薄汚れた老婆が、工場(?)から連れ出され、まるで収容所に向かうかのような荷車に乗せられる。オペラ劇場のような所に、進行役の身なりの良い男が現れ、「新しい着想を得た」と語りはじめる。それは、クラシックの名曲をアニメーションで表現しようという、実に「斬新な」思いつきだ。ところが電話がなる。ハリウッドのプリズニーだかなんだかという男がすでにそういう映画を作っているというのだ。この辺りからして笑いが込み上げる。しかし男はめげずに、オーケストラと指揮者と、アニメータを用意する。オーケストラは、さきほどの老婆たちだ。昔風の無気味な衣裳を来て、なんと古楽器(大昔の竪琴とか)を手に「ヌードは断った」とか「貞操は守ったとか」ゴシップを話している。指揮者はそうとうエキセントリックで暴力的な大柄の男。そしてアニメーターは、地下牢で壁に繋がれていた気弱で神経質そうな男というメンバー。このメンバーでのドタバタ劇(フェリーニ風と評されていた)を間に挟みながら6曲の作品が紹介される。演奏と解説がリアルタイムでアニメにつながる雰囲気は本家『ファンタジア』に合わせているが、いきなりゴリラが現れて指揮者を襲ったり、進行役が連れて来た売春婦とアニメーターがピアノの中で事に及んだりと(ピアノが使われる曲はない)、食事の時間と称して配給食のようなスープが出て来たりと、なんとも非ディズニー的である。ただ、そういったドタバタのやり取りの中から、アニメーターが次の曲の着想を得て、描いて行く過程は、音楽=アニメパートにすんなりとつながっている。
「カラフルなアニメとクラシック音楽の美しく華麗な融合」を期待していると、いきなり虚を突かれる。なんとも暗い雰囲気のモノクロの実写パートが始まるのだ。バケツと雑巾を手にオペラ劇場の床をふく少女(ヒロインか?)。数十人の薄汚れた老婆が、工場(?)から連れ出され、まるで収容所に向かうかのような荷車に乗せられる。オペラ劇場のような所に、進行役の身なりの良い男が現れ、「新しい着想を得た」と語りはじめる。それは、クラシックの名曲をアニメーションで表現しようという、実に「斬新な」思いつきだ。ところが電話がなる。ハリウッドのプリズニーだかなんだかという男がすでにそういう映画を作っているというのだ。この辺りからして笑いが込み上げる。しかし男はめげずに、オーケストラと指揮者と、アニメータを用意する。オーケストラは、さきほどの老婆たちだ。昔風の無気味な衣裳を来て、なんと古楽器(大昔の竪琴とか)を手に「ヌードは断った」とか「貞操は守ったとか」ゴシップを話している。指揮者はそうとうエキセントリックで暴力的な大柄の男。そしてアニメーターは、地下牢で壁に繋がれていた気弱で神経質そうな男というメンバー。このメンバーでのドタバタ劇(フェリーニ風と評されていた)を間に挟みながら6曲の作品が紹介される。演奏と解説がリアルタイムでアニメにつながる雰囲気は本家『ファンタジア』に合わせているが、いきなりゴリラが現れて指揮者を襲ったり、進行役が連れて来た売春婦とアニメーターがピアノの中で事に及んだりと(ピアノが使われる曲はない)、食事の時間と称して配給食のようなスープが出て来たりと、なんとも非ディズニー的である。ただ、そういったドタバタのやり取りの中から、アニメーターが次の曲の着想を得て、描いて行く過程は、音楽=アニメパートにすんなりとつながっている。