戞俁復乽妝晥偺堄媊乿丂懕偒丂
4.尰戙偺妝晥
丂偙偺傛偆偵妝晥偺堄媊偼丄壒妝偺婰榐丄嵞尰丄曐懚丄嶌昳偲偟偰偺嫆傝強丄偦偟偰丄嶌嬋偺彂朄偲嫟偵曕傫偱偒偨嶌嬋偺曣懱偲偟偰偺壙抣偱偁偭偨丅偦偟偰丄偙傟傜偼丄嫟捠惈偺忋偵巒傔偰惉傝棫偮僐乕僪偱偁偭偨丅150擭偲偄偆惣梞壒妝揮姺偺扨埵偐傜偡傟偽丄1750擭偵偼偠傑傞屆揟攈丒儘儅儞攈偺帪戙偼丄1900擭偵廔鄟傪岦偐偊傞偙偲偵側傞丅妋偐偵丄20悽婭偵擖傝丄惣梞壒妝偼丄傑偨戝偒側揮姺傪岦偐偊偨丅偦偺揮姺偼丄1908擭丄傾儖僲儖僩丒僔僃乕儞儀儖僋Arnold Schonberg (1874-1951)偵傛偭偰側偝傟傞丅偙偺帪戙丄婡擻榓惡朄偵傛傞榓壒偺楢寢偼丄偡偱偵丄尷奅揰傑偱奼挘偟偰偄偨丅儕僸儍儖僩丒償傽僌僫乕 Richard Wagner(1813-1883)偼丄婡擻榓惡偺揮挷傪尷傝側偔暋嶨偵楢寢偝偣傞偙偲偱丄僋儘乕僪丒僪價儏僢僔乕 Claude Debussy(1862-1918)偼丄榓惡偺婡擻揑摥偒傛傝丄偦傟偧傟偺嬁偒傪廳帇偡傞偙偲偱丄惣梞壒妝偑挿擭偵傢偨傝偐偐偊偰偒偨挷惈偲偄偆奣擮傪夞旔偟偰偄偭偨丅偟偐偟丄挷惈偑姶庴偟偵偔偄偲偄偆帠偲丄挷惈偑柍偄偲偄偆偙偲偼傑偭偨偔摍偟偔側偄乵拲64乶 丅柍挷 atonality偲偄偆奣擮偼丄傑偭偨偔崱傑偱偺壒偺慻怐曽朄偲偼堎側傞丅12壒媄朄偲偟偰丄偙傟傪懱宯壔偟偨偺偑丄僔僃乕儞儀儖僋偱偁偭偨丅婡擻榓惡偱偼丄奺乆偺壒偵栶妱偑偁傞丅庡壒 tonic偲懏壒 dominant偼丄嵟傕廳梫側壒偱丄挷惈傪巟攝偡傞丅偙傟偼丄僴挿挷偱尵偊偽丄C偲G偵偁偨傞丅摨條偵壓懏壒 subdominant 乮F乯傕廳梫偱偁傞丅摫壒 leading tone偼丄偦偺柤偺偲偍傝丄埨掕偟偨壒傊抁擇搙偺忋峴偱恑峴偡傞壒乮H乯偱偁傞丅偙偺傛偆側晄暯摍側庢傝埖偄偐傜丄壒傪夝曻偟偨偺偑丄12壒媄朄偱偁傞丅偙偺棟榑偱偼丄壒奒拞偺12偺壒偑慡偰摍偟偄堄枴傪帩偮丅偟偨偑偭偰丄拞怱壒偼懚嵼偣偢丄挷惈偼惗傑傟側偄丅億儕僼僅僯乕偑儂儌僼僅僯乕偵側傞嵺丄妋偐偵丄椉幰偺娫偵偼丄奣擮揑偵憡斀偡傞晹暘偑偁偭偨丅偟偐偟丄偦傟偼壒妝忋偱偼丄嫟惗偱偒傞傕偺偱偁傝丄偳偪傜偐偺懚嵼偑丄懠曽偺懚嵼傪斲掕偡傞偲偄偆傕偺偱偼側偐偭偨丅偟偐偟丄偦傟偱傕丄壒妝偺條幃偵崌傢偣丄婰晥朄偼曄壔傪偟偨丅攺巕婰崋偑尰傢傟丄彫愡慄偑傂偐傟傞傛偆偵傕側偭偨丅偟偐偟丄偙偺儂儌僼僅僯乕偐傜12壒壒妝傪堄枴偡傞僪僨僇僼僅僯乕 dodecaphony 傊偺堏峴偵偍偄偰偼丄婰晥朄偼丄曄壔傪偆偗側偐偭偨偺偱偁傞丅12壒媄朄偼丄夁嫀偺偳傫側壒妝偲傕傑偭偨偔暿偺懱宯偐傜側偭偰偄傞偺偵傕偐偐傢傜偢偱偁傞丅偙偺婰晥朄偺曄慗偺椺奜偵偼丄偳傫側棟桼偑偁傞偺偩傠偆偐丅
丂12壒媄朄偱偼丄傑偢丄嶌嬋壠偼丄憡堘偡傞12壒傪慡偰娷傓僙儕乕偲屇偽傟傞壒楍傪偮偔傞丅偙偺僙儕乕偼儕僘儉傪傕偨側偄拪徾揑側傕偺偲偟偰埖傢傟丄條乆側曄宍傪偆偗丄嵟廔揑偵1偮偺僙儕乕偐傜48庬偺壒楍偑宍惉偱偒傞傢偗偱偁傞乵拲65乶丅偙偺壒楍偼丄墶曽岦偵慁棩偲偟偰丄廲曽岦偵榓壒偲偟偰廳偹傞偙偲傕弌棃傞偺偩偑丄壒壙偼偙偺懱宯偵偼娷傑傟偰偄側偄丅偁偔傑偱傕丄壒掱娭學傪婎慴偲偟偰偄傞媄朄偩偐傜偱偁傞丅嬤戙晥朄偼丄壒偺崅偝偵偮偄偰偼丄姰惉偝傟偨婰晥懱宯傪丄壒壙偺偦傟埲慜偵庤偵擖傟偰偄偨丅偮傑傝丄壒妝忋偺丄傕偟偐偟偨傜丄嵟戝偺曄壔偵丄婰晥忋偺曄壔偑敽傢側偄傎偳丄嬤戙晥朄偼怣棅偝傟偰偄偨偺偱偁傝丄偙偙傑偱偺婰晥懱宯傪摼傞偲丄偦傟傪攋夡偡傞昁梫傪擣傔傜傟側偐偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄幚偼丄傑偭偨偔栤戣偑側偄傑傑丄偙偺傛偆側壒妝條幃偺僐儁儖僯僋僗揑揮姺偑壜擻偩偭偨偺偱偁傠偆偐乵拲66乶丅
丂偦傕偦傕丄嬤戙偺妝晥偑丄堦斒揑偵屲慄晥偲屇偽傟傞傛偆偵丄偦偺嵟戝偺摿挜偼丄屲杮偺慄偱帵偝傟傞嬻娫揑側壒偺埵抲偺攃埇宍懺偵偁傞丅壒晹婰崋偵傛偭偰丄巜帵偝傟傞丄慄忋偵G傑偨偼F丄C偺壒傪抲偒丄偦偺嶰搙偯偮忋偺壒偑丄慄忋偵偔傞偲偄偆曽朄偱偁傞丅壒晹婰崋偑僩壒婰崋偺応崌丄壓偐傜丄E丄G丄B丄D丄F偑慄忋偵偁偨傞偙偲偵側傞丅偙偺嶰搙偛偲偺慄偲偄偆峫偊曽偼丄偪傚偆偳丄壒偺挿偝偑丄嶰暘妱偝傟傞丄姰慡暘妱偲摨條偵丄嶰偲偄偆悢帤偺帩偮丄晄壜怤側惛恄揑梫慺偵傛偭偰偄傞偺偩偑丄壒壙偵偍偗傞嶰偺巟攝偼柍偔側偭偰傕壒崅偵娭偟偰偼丄懚懕偟偰偟傑偭偨丅偦偺偨傔丄慄忋偺E丄G丄B丄D丄F偼丄嶰搙偲偼尵偭偰傕丄幚嵺偼丄G-B娫偺壒掱偑丄挿嶰搙偱偁傝丄偁偲偼丄抁嶰搙偲偄偆暿偺壒掱傪帩偮偙偲偵側傞丅傕偭偲暘偐傝傗偡偔尵偊偽丄拞墰偺C偺壒偼丄壓慄偲屇偽傟傞慄忋偵偁傞偑丄偦偺堦僆僋僞乕僽忋偺C偼丄慄忋偱偼側偔丄慄娫偵埵抲偡傞偙偲偵側傞丅偦偟偰丄傑偭偨偔暿偺壒偱偁傞G傕丄Gis(僜#)傕丄Ges(僜侒)傕摨偠丄慄忋偵懚嵼偡傞偙偲偵側傝丄摨偠壒偱偁傞Gis偲As(儔侒)偼丄暿偺埵抲偵偔傞偙偲偵側傞乵拲67乶 丅偟偨偑偭偰丄婡擻榓惡揑偵丄偙傟傜傪暘暿偟丄僔儍乕僾丄僟僽儖丒僔儍乕僾丄僼儔僢僩丄僟僽儖丒僼儔僢僩偲偄偆曄壔婰崋偲丄偦傟傪尦偵栠偡丄僫僠儏儔儖偑梡偄傜傟傞偑丄敿壒奒傪懡梡偡傞壒妝偱偼丄偙偺婰晥朄偼斚嶨側傕偺偲側傜偞傞傪摼側偄丅摿偵丄12壒壒妝偼丄敿壒偑丄傕偭偲傕婎杮揑側壒偺扨埵側偺偱丄偙偺婡擻榓惡朄偵婎偯偄偨屲慄晥偺僔僗僥儉偼丄尌偵奊偺嬶傪梟偄偰巊偆傛偆側傕偺偩偭偨偺偱偁傞丅晥椺3-2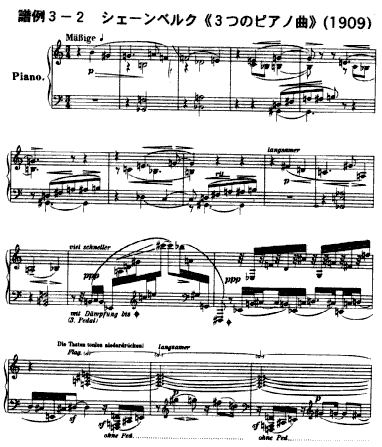 偼丄僔僃乕儞儀儖僋偺僺傾僲嬋偺堦晹偱偁傞偑丄偙偙偱偼丄偁傜偐偠傔僼儔僢僩傗僔儍乕僾偑偮偄偰偄側偄偵傕娭傢傜偢丄僫僠儏儔儖偑昿斏偵巊傢傟偰偄傞丅傛偔尒偰偄偨偩偔偲暘偐傞傛偆偵丄僔儍乕僾丄僼儔僢僩偍傛傃僫僠儏儔儖偺偮偄偰偄側偄壒晞偼側偄丅偮傑傝偦偺巚憐偑帵偡偲偍傝丄偡傋偰偺壒晞偑暯摍偵埖傢傟偰偄傞丅偟偐偟丄偦偺暯摍偼丄婰晥忋偱偺丄壒崅偺壜帇壔偵嬶懱壔偝傟傞偙偲偼側偄丅幚嵺丄敿壒傪暯摍偵婰弎偱偒傞妝晥偼丄僆儔儞僟偺媄巘僐儖僱儕僗丒億乕僩 Cornelis Pot偵傛偭偰敪柧偝傟偨僋儔償傽乕儖僗僋儕乕儃 Klavarskribo乵拲68乶 偩偗偱偼側偄偩傠偆偐丅僋儔償傽乕儖僗僋儕乕儃偱偼丄仠偲仜偵傛偭偰壒奒忋偺壒偲丄偦傟偵懳偟丄僔儍乕僾丄僼儔僢僩偺偮偄偨壒偑嬫暿偝傟偰偄傞偑丄偟偐偟丄悅捈偵堷偐傟偨屲杮偺慄偑丄偪傚偆偳丄僺傾僲偺尞斦偺傛偆偵丄偦傟偧傟偺壒傪暘暿偟偰偄傞丅G偲Ges偼丄暿偺埵抲偵偔傞偙偲偵側傞丅 晥椺3-3
偼丄僔僃乕儞儀儖僋偺僺傾僲嬋偺堦晹偱偁傞偑丄偙偙偱偼丄偁傜偐偠傔僼儔僢僩傗僔儍乕僾偑偮偄偰偄側偄偵傕娭傢傜偢丄僫僠儏儔儖偑昿斏偵巊傢傟偰偄傞丅傛偔尒偰偄偨偩偔偲暘偐傞傛偆偵丄僔儍乕僾丄僼儔僢僩偍傛傃僫僠儏儔儖偺偮偄偰偄側偄壒晞偼側偄丅偮傑傝偦偺巚憐偑帵偡偲偍傝丄偡傋偰偺壒晞偑暯摍偵埖傢傟偰偄傞丅偟偐偟丄偦偺暯摍偼丄婰晥忋偱偺丄壒崅偺壜帇壔偵嬶懱壔偝傟傞偙偲偼側偄丅幚嵺丄敿壒傪暯摍偵婰弎偱偒傞妝晥偼丄僆儔儞僟偺媄巘僐儖僱儕僗丒億乕僩 Cornelis Pot偵傛偭偰敪柧偝傟偨僋儔償傽乕儖僗僋儕乕儃 Klavarskribo乵拲68乶 偩偗偱偼側偄偩傠偆偐丅僋儔償傽乕儖僗僋儕乕儃偱偼丄仠偲仜偵傛偭偰壒奒忋偺壒偲丄偦傟偵懳偟丄僔儍乕僾丄僼儔僢僩偺偮偄偨壒偑嬫暿偝傟偰偄傞偑丄偟偐偟丄悅捈偵堷偐傟偨屲杮偺慄偑丄偪傚偆偳丄僺傾僲偺尞斦偺傛偆偵丄偦傟偧傟偺壒傪暘暿偟偰偄傞丅G偲Ges偼丄暿偺埵抲偵偔傞偙偲偵側傞丅 晥椺3-3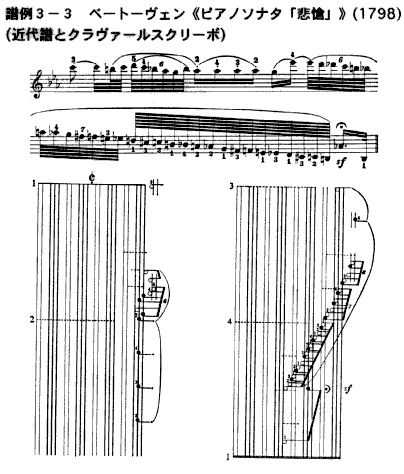 偼丄儀乕僩乕償僃儞偺乻僺傾僲僜僫僞戞俉斣乬斶溒乭 Sonate fur Klavier No.8 "Pathetique"乼(1798-1799)偺嬤戙晥朄偲僋儔償傽乕儖僗僋儕乕儃偺懳斾椺偱偁傞丅壒偺崅偝偑丄嬻娫揑斾歡傪棙梡偟偰壜帇揑偵昞尰偝傟傞偲偄偆側傜偽丄堎側傞壒偼丄堎側傞嬻娫偵偁傞偺偑摉慠偺巔偱偁傞丅屻敿偺敿壒奒偵傛傞壓崀宍偵柧傜偐側傛偆偵丄僋儔償傽乕儖僗僋儕乕儃偼丄尒帠偵偦偺梫惪傪壥偨偟偰偄傞丅偟偐偟丄偙偺僋儔償傽乕儖僗僋儕乕儃偼丄傑偭偨偔晛媦偟偰偄側偄偲偄偭偰傕椙偄丅嬤戙晥朄偑偄偐偵丄愨懳揑尃埿偺傛偆偵巚傢傟偰偄傞偐傪徹柧偡傞偙偲偵傕側傞偑丄棟榑揑偵尵偭偰傕丄偙偺曽朄偼丄夋婜揑偱偼偁傞偑丄壒妝條幃偺堏峴偵偲偭偰妀怱揑側夝寛偵偼側傜側偐偭偨偽偐傝偐丄偦偺屻偺媫寖側壒妝條幃偺曄壔偵懳墳偱偒側偔側偭偨偐傜偱偁傞丅
偼丄儀乕僩乕償僃儞偺乻僺傾僲僜僫僞戞俉斣乬斶溒乭 Sonate fur Klavier No.8 "Pathetique"乼(1798-1799)偺嬤戙晥朄偲僋儔償傽乕儖僗僋儕乕儃偺懳斾椺偱偁傞丅壒偺崅偝偑丄嬻娫揑斾歡傪棙梡偟偰壜帇揑偵昞尰偝傟傞偲偄偆側傜偽丄堎側傞壒偼丄堎側傞嬻娫偵偁傞偺偑摉慠偺巔偱偁傞丅屻敿偺敿壒奒偵傛傞壓崀宍偵柧傜偐側傛偆偵丄僋儔償傽乕儖僗僋儕乕儃偼丄尒帠偵偦偺梫惪傪壥偨偟偰偄傞丅偟偐偟丄偙偺僋儔償傽乕儖僗僋儕乕儃偼丄傑偭偨偔晛媦偟偰偄側偄偲偄偭偰傕椙偄丅嬤戙晥朄偑偄偐偵丄愨懳揑尃埿偺傛偆偵巚傢傟偰偄傞偐傪徹柧偡傞偙偲偵傕側傞偑丄棟榑揑偵尵偭偰傕丄偙偺曽朄偼丄夋婜揑偱偼偁傞偑丄壒妝條幃偺堏峴偵偲偭偰妀怱揑側夝寛偵偼側傜側偐偭偨偽偐傝偐丄偦偺屻偺媫寖側壒妝條幃偺曄壔偵懳墳偱偒側偔側偭偨偐傜偱偁傞丅
丂傑偢丄壒崅偺奼戝偱偁傞偑丄廬棃偺壒崅昞帵偵偲偭偰12壒媄朄埲忋偵栵夘側栤戣偑偁傞丅椺偊偽丄愭偵椺帵偟偨丄捁偺惡傗恖偺夛榖側偳丄尦棃丄挷惈偺側偄傕偺偱傕丄妝晥偼丄壒偲偟偰婰弎偱偒傞偲偄偭偨丅偟偐偟丄偦傟偼丄幚嵺偼丄捁偺惡丄堦偮堦偮傪妝晥偵彂偒昞傢偣傞嵟傕嬤偄壒偵丄僷儔僼儗乕僘偟偰偄傞偵偡偓側偄丅G偱傕Gis偱傕側偄偦偺娫偺傛偆側壒偼丄壒掱揑偵柍帇偝傟傞丅偙偺敿壒傛傝嫹偄壒掱傪旝暘壒掱 microtonal interval偲屇傇偺偩偑丄婰晥朄傪敪払偝偣丄暯嬒棩傪惍偊丄婡擻榓惡傪揥奐偝偣偰偄偔夁掱偱丄旂擏偵傕丄惣梞壒妝偼丄偙偺敿壒傛傝彫偝偄壒偺扨埵傪搼懣偟偰偟傑偭偨丅偙傟傜偼丄儁儖僔傾傗僀儞僪丄擔杮偱傕丄晛捠偵巊傢傟偰偄傞壒掱偱偁傞丅惣梞偱傕丄20悽婭偺偼偠傔偛傠偐傜丄慡壒偵懳偟偰偺暘妱悢偵傛偭偰嶰暘壒丄巐暘壒丄榋暘壒側偳偑僼僃儖僢僠儑丒僽僝乕僯 Ferruccio Busoni (1866-1924) 傗傾儘僀僗丒僴乕僶 Alois Haba (1893-1973) 偵傛偭偰拲栚偝傟巒傔丄崱擔偺壒妝偱偼丄昗弨揑側媄朄偵側偭偰偄傞丅僋儔償傽乕儖僗僋儕儃偼丄敿壒偺婰弎偵惉岟偟偨偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄偙偺怴偟偄壒掱偵娭偟偰偺婰弎偺崲擄偝偱偼丄屲慄晥朄偲側傫傜堎側傞偙偲偼側偄偺偱偁傞丅傕偪傠傫丄偙傟傪屲慄忋偵昞傢偡偨傔偵偼摿庩側婰晥朄偼懚嵼偡傞丅僴乕僶偺峫埬偵側傞巐暘壒偺婰晥朄乮晥椺3-4乯 偑桳柤偩偑懠偵傕丄庬椶偑偁傝丄尰戙偵側傞偵偮傟丄偦偺旝暘搙偼丄偙傑偐偔丄惛枾偝傪梫媮偝傟傞傛偆偵側傞丅偙偆側傞偲丄堦懱丄偄偔偮偺堎側傞崅偝傪帩偮壒偑丄摨偠晥柺忋偺埵抲偵婰弎偝傟傞偙偲偵側傞偺偱偁傠偆偐丅
偑桳柤偩偑懠偵傕丄庬椶偑偁傝丄尰戙偵側傞偵偮傟丄偦偺旝暘搙偼丄偙傑偐偔丄惛枾偝傪梫媮偝傟傞傛偆偵側傞丅偙偆側傞偲丄堦懱丄偄偔偮偺堎側傞崅偝傪帩偮壒偑丄摨偠晥柺忋偺埵抲偵婰弎偝傟傞偙偲偵側傞偺偱偁傠偆偐丅
丂偝傜偵丄12壒媄朄偐傜惗傑傟偨壒楍偵傛偭偰壒妝傪峔惉偡傞偲偄偆尨棟偼丄屻偵丄僙儕乕壒妝 musique serielle傪惗傓丅娙扨偵尵偊偽丄僙儕乕乮楍乯傪壒崅埲奜偵傕揔梡偡傞偺偑丄12壒媄朄偲偺嵎側偺偩偑丄偙偙偱丄壒崅偵婲偙偭偨奼戝偑丄壒壙丒嫮搙丒壒怓偵傕婲偙傞傛偆偵側傞丅慡偰偺壒傪暯摍側慺嵽偲偟偰埖偆偙偲偱丄婡擻榓惡偼徚偊嫀偭偨偑丄壒壙傗嫮搙傪暯摍偵埖偊偽丄攺愡傗儕僘儉偺傛偆側廬棃偺帪娫奣擮偑丄曵夡傊偺摴傪扝傞丅儊僔傾儞偺乻壒壙偲嫮搙偺儌乕僪 Mode de valeurs et d'intensites乼(1949)偺堦偮偺僙儕乕傪墳梡偟丄僺僄乕儖丒僽乕儗乕僘 Pierre Boulez ( 1925-)偺乻2戜偺僺傾僲偺偨傔偺僗僩儕儏僋僥儏乕儖厽 Structures pour deux pianos厽乼(1952) 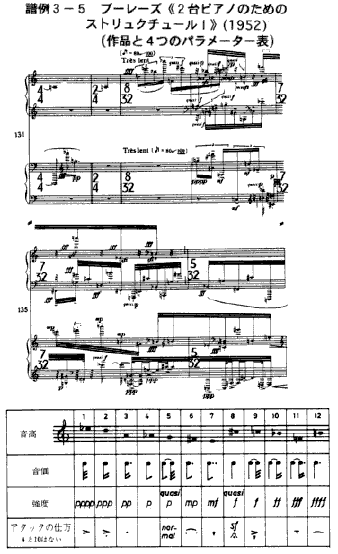 偑丄偦傟傪巒傔偰梡偄偨壒妝偲偝傟傞丅斵偼丄巘偺壒崅傪僷儔儊乕僞乕偲偡傞僙儕乕傪丄壒壙丒嫮搙丒壒怓偵妱傝摉偰傞堦偮偺曽朄榑傪帵偟偨偺偱偁傞丅偙傟偼屻偺丄僙儕傾儕僗僩偵偲偭偰偺惞彂偲側偭偨丅晥椺3-5偑丄偦偺妝晥偩偑丄揧晅偝傟偨昞偺傛偆偵丄壒崅丄壒壙丄嫮搙丄傾僞僢僋偺巇曽偑僙儕乕壔偝傟丄廬棃偺榓惡宍懺傗儕僘儉偲偼暿庬偺壒嬁偑嶌傜傟偰偄傞丅
偑丄偦傟傪巒傔偰梡偄偨壒妝偲偝傟傞丅斵偼丄巘偺壒崅傪僷儔儊乕僞乕偲偡傞僙儕乕傪丄壒壙丒嫮搙丒壒怓偵妱傝摉偰傞堦偮偺曽朄榑傪帵偟偨偺偱偁傞丅偙傟偼屻偺丄僙儕傾儕僗僩偵偲偭偰偺惞彂偲側偭偨丅晥椺3-5偑丄偦偺妝晥偩偑丄揧晅偝傟偨昞偺傛偆偵丄壒崅丄壒壙丄嫮搙丄傾僞僢僋偺巇曽偑僙儕乕壔偝傟丄廬棃偺榓惡宍懺傗儕僘儉偲偼暿庬偺壒嬁偑嶌傜傟偰偄傞丅
丂偝傜偵丄揹巕壒嬁媄弍偺敪払偵傛傝丄偦傟傜偺壒偺梫慺偼偝傜偵丄奼戝偡傞丅椺偊偽丄壒偺埵憡偱偁傞丅偮傑傝丄暦偙偊偰偔傞曽妏傗壒尮偐傜偺嫍棧乮偦傟傜偼堏摦偡傞偙偲傕摉慠偁傝偆傞乯側偳偱偁傞丅晳戜棤偱偺墘憈丄媞惾僶儖僐僯乕偱偺墘憈丄偙傟傜偼丄僶儞僟 banda 偲屇偽傟丄愄偐傜懚嵼偡傞偑丄偙傟傪僙儕乕壔偡傞偙偲偼丄揹巕壒嬁偵傛偭偰側偝傟偨偲偄偊傞丅
丂壒妝偑丄偙偙傑偱偺忣曬傪娷桳偡傞傛偆偵側偭偰傕側偍丄婰晥朄偼丄嬤戙屲慄晥偐傜丄曄壔偟側偄偺偩傠偆偐丅
俆丏恾宍妝晥偲婰晥朄偺枹棃
丂壒崅傗壒壙側偳偺壒妝偺梫慺傪僷儔儊乕僞乕偲屇傇傛偆偵側傞偲丄壒妝傪丄悢抣壔偝傟偨僷儔儊乕僞乕偺廤傑傝偲偟偰婰弎偱偒傞偙偲偑暘偐傞丅壒崅偼丄廃攇悢傪廲幉偵偲傞偙偲偱丄壒壙偼昩悢傪墶幉偵偲傞偙偲偱丄旝嵶側壒掱傕丄愨懳揑側壒壙傕巟攝偡傞偙偲偑偱偒傞丅晥椺3-6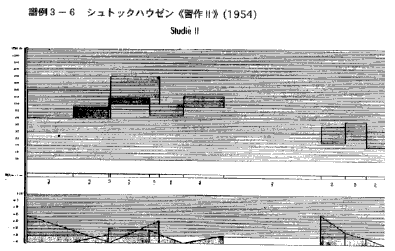 偺僇儖儖僴僀儞僣丒僔儏僩僢僋僴僂僛儞 Karlheinz Stockhausen(1928-)偺乻廗嶌2 Studien厾乼(1953-54)偑傑偝偵偦傟偱偁傞丅壒崅偼100乣17200Hz偺娫偺81杮偺慄偱丄壒壙偼僥乕僾偺憱峴懍搙丄76.2cm/sec傪僙儞僠儊乕僩儖偱巜帵丄嫮搙偼侾杮偑侾僨僔儀儖傪帵偡-40乣0dB偵偄偨傞慄偵傛偭偰丄偦偺堏峴乮傾僑乕僊僌乯偲偲傕偵丄偁傜傢偝傟偰偄傞丅
偺僇儖儖僴僀儞僣丒僔儏僩僢僋僴僂僛儞 Karlheinz Stockhausen(1928-)偺乻廗嶌2 Studien厾乼(1953-54)偑傑偝偵偦傟偱偁傞丅壒崅偼100乣17200Hz偺娫偺81杮偺慄偱丄壒壙偼僥乕僾偺憱峴懍搙丄76.2cm/sec傪僙儞僠儊乕僩儖偱巜帵丄嫮搙偼侾杮偑侾僨僔儀儖傪帵偡-40乣0dB偵偄偨傞慄偵傛偭偰丄偦偺堏峴乮傾僑乕僊僌乯偲偲傕偵丄偁傜傢偝傟偰偄傞丅
丂偙傟傜偺丄揹巕壒妝偺妝晥偼丄偦偺惈幙偐傜恾宍妝晥 graphic score偲屇偽傟偰偄傞丅尰戙壒妝忋丄傕偭偲傕廳梫側婰晥朄偑丄恾宍妝晥偱偁傠偆丅乽壒妝偺曄梕偲嫟偵丄偐偮偰僱僂儅晥偐傜掕検婰晥朄偵堏偭偨偺偲摨偠偙偲偑丄崱擔丄嵞傃婲偙傞昁慠惈偑偁傞乿偲僔儏僩僢僋僴僂僛儞偑尵偭偰偄傞偺偼丄傑偝偵丄嬤戙屲慄晥朄偐傜偺丄恾宍妝晥傊偺堏峴偺偙偲偵懠側傜側偄丅偟偐偟丄恾宍妝晥偲偄偆尵偄曽偼丄濨枂側堄枴偟偐帩偭偰偄側偄丅帿彂偵偼丄乽屲慄晥傪梡偄偢偵丄婰崋傗恾宍偱昞傢偝傟偨妝晥乿偲彂偄偰偁傝丄偦傟偑丄恾宍妝晥偺慡偰偱偁傞丅偮傑傝偦傟偼丄嬤戙屲慄晥傪巊傢偢偵彂偐傟偨尰戙偺偁傜備傞妝晥傪娷傓偐傜偱偁傞丅揹巕壒妝偩偗偱偼側偔丄嬼慠惈偺壒妝 chance music 偲屇偽傟傞條幃偵傕懡梡偝傟傞丅壒妝偵偼丄僕儍儞儖丄條幃丄宍幃丄峔憿側偳偵傛偭偰丄條乆側柤徧偑梌偊傜傟丄変乆偺棟夝傪崿棎偝偣傞傕偺偩偑丄偙偙偱搊応偡傞柤徧傕丄傑偝偵暋嶨偒傢傑傝側偄傕偺偱偁傞丅揹巕壒妝偲偄偆偺偼丄揹巕壒嬁婡婍偵傛偭偰壒嬁張棟傪峴偄丄帴婥僥乕僾偵掕拝偝偣偨壒妝傪偝偡堦偮偺壒妝僕儍儞儖偱偁傞丅偟偐偟丄偦傟偼丄墘憈偝傟側偄丄偲偄偆廳梫側條幃傪娷傓丅偟偨偑偭偰丄挳妎揑偵偼丄偦偺揹巕壒偑摿挜揑偩偑丄揹巕妝婍乵拲69乶 傪巊梡偟偰偄傞偐傜偲偄偭偰揹巕壒妝偲偼尵傢側偄丅嬼慠惈偺壒妝偲偼丄墘憈偵嵺偟偰丄墘憈壠偺擟堄側夝庍傗懄嫽偺壙抣傪擣傔傞壒妝傪巜偡丅堦搙偒傝偺壒尰徾傪廳帇偡傞曽朄榑偱偁傝丄揹巕壒妝偲偼丄奣擮揑偵懳棫偡傞丅
丂偙偺擇偮偺尰戙偺條幃偼丄妝晥偺堄媊偵偲偭偰廳戝側栤戣傪搳偘偐偗偰偔傞丅乽墘憈偝傟側偄乿揹巕壒妝偲丄乽姰慡偵嶌嬋偝傟側偄乿嬼慠惈偺壒妝丅偦偟偰丄偙偺擇偮偺壒妝偺婰晥朄偲偟偰抦傜傟傞恾宍妝晥偱偁傞丅偙偺偙偲偼丄婰晥朄偺堄媊傗丄偦偺枹棃偵偲偭偰幚偵帵嵈揑偱偁傞丅崱屻偺媍榑偱偼丄暣傜傢偟偝傪側偔偡偨傔丄偦偺壒妝偲偼愗傝棧偟偰丄揹巕壒妝偺妝晥傪僷儔儊乕僞乕揑妝晥丄嬼慠惈偺壒妝偑梡偄傞妝晥傪僌儔僼傿僢僋揑妝晥偲嬫暿偡傞偙偲偵偟傛偆丅偨偩偟丄偙傟傜偺恾宍妝晥偵嫟捠偡傞偙偲偼丄撉晥偺忋偱丄摑堦揑側尨懃偑懚嵼偟側偄偲偄偆偙偲偩丅偳偪傜傕丄偦偺妝晥傪嶌傝弌偟偨恖丄偮傑傝嶌嬋壠偵傛偭偰丄偦偺曽朄偑丄拃堦婯掕偝傟丄愢柧偝傟傞傕偺側偺偱偁傞丅
丂偝偰丄偙偺恾宍妝晥偺峫嶡偼丄杮榑偺嵟廔抜偵偲偭偰傕廳梫側堄枴傪帩偮丅杮榑偺僥乕儅偱偁傞丄壒妝偺壜帇壔偲婰晥朄偺娭楢傪丄尰戙揑側婰晥朄偵懄偟偰夝撉偡傞偙偲偵丄師偓偺擇偮偺懳徾娭學傪尒偄弌偡偙偲偑偱偒丄偦傟偼丄夁嫀偺婰晥朄偵娭偟偰傕丄帵嵈偵晉傫偱偄傞偲巚傢傟傞偐傜偱偁傞丅偙偙偱丄巹偑採帵偟偨偄娭學偼丄乽儊僩儕僢僋乿懳乽僷儔儊僩儕僢僋乿丄偦偟偰丄乽壒偺壜帇壔乿懳乽峴堊偺巜帵乿偲偄偆娭學偱偁傞丅
丂壢妛傗悢妛傪懳徾偵偟偰偄傞偺偱偼側偄偺偱丄儊僩儕僢僋傗僷儔儊僩儕僢僋偲偄偆尵梩傪丄悢妛揑惓妋偝偱丄巊梡偡傞傢偗偱偼側偄偺偩偑丄偙偙偱偺丄儊僩儕僢僋偼検揑側傕偺傪巜偟丄僷儔儊僩儕僢僋偼悢揑側傕偺傪巜偡偲偄偆掱搙偵峫偊偰傎偟偄丅
丂僱僂儅偼壒偺壜帇壔傪乽儊僩儕僢僋乿偵峴偭偨偲尵偊傞丅 晛捠丄儊僩儕僢僋偲偄偆尵梩偼丄掕検婰晥朄偲偲傕偵巊傢傟傞偺偩偑丄悇掕揑儊僩儕僢僋偲尵偊偽丄僱僂儅偵傕丄捠梡偡傞偩傠偆丅僺僄乕儖丒僽乕儗乕僘偑丄僱僂儅揑側僔僗僥儉偼丄柍掕宍側帪娫傗妸傜偐側帪娫偺曽傪柧傜偐偵偡傞偺偵揔偟偰偄傞乵拲70乶 偲偄偆傛偆偵丄僱僂儅偺慄昤揑側婰晥朄偼丄帇妎偵傛偭偰敾抐偝傟傞丄傛傝悇掕揑側徾挜偱偁傞丅偙偺偔傜偄偲偄偆検偱偁傞丅堦曽偺掕検婰晥朄偼丄弮悎側堄枴偱丄偮傑傝丄應掕揑側儊僩儕僢僋偱偁偭偨丅壒掱娭學傕丄壒壙傕丄偦傟偼撪揑偵斾妑偝傟傞検偱偁傝丄検偼晄暯摍傪峔抸偡傞丅
丂19悽婭偵擖傝丄嶌嬋壠偲墘憈壠偼丄姰慡偵暘嬈偝傟傞丅偙偆側傞偲丄嶌嬋壠偼丄帺暘偺壒妝傪丄婰弎忋偵姰慡偵掕拝偝偣側偗傟偽側傜側偄丅偙偺帪戙丄妝晥偵嵟弶偺乽僷儔儊僩儕僢僋乿偑帩偪崬傑傟偨丅偦偺嶌嬋壠偼儖乕僪償傿僸丒償傽儞丒儀乕僩乕償僃儞 Ludwig van Beethoven(1770-1827)偱偁傞丅儀乕僩乕償僃儞偼丄僥儞億偲偄偆奣擮傪僷儔儊僩儕僢僋偵偡傞偙偲偱丄姶妎揑壒妝偺悽奅偵僷儔儊乕僞乕傪帩偪崬傫偩丅斵偺儊僩儘僲乕儉婰崋乵拲71乶 偼丄帊傪撉傓嵺偺塁棩偱偺帪娫寁應傗丄乽曕偔傛偆偵 Andante乿偲偄偆曕峴偺儁乕僗偱婯掕偝傟偨懍搙昗岅乵拲72乶 偲偼丄傑偭偨偔堎側傞峫偊曽偵婎偯偔丅廬棃偺恖娫偵撪嵼偡傞姶妎揑懍搙昞帵偼丄儊僩儕僢僋側傕偺偲偟偰丄婰晥朄傪惗傒偩偟偨丅廬棃偺巚峫偱偼丄偦傟偼丄妝晥偲偄偆儊僨傿傾偺拞偵偍偄偰丄偦傟偧傟偵丄儊僩儕僢僋側傕偺偱偁傝丄偦偺奜晹峔憿傪巟攝偡傞傕偺偱偼側偐偭偨丅検傪寁應偡傞儊僩儕僢僋側傕偺偲偟偰丄偦傟偧傟偵娭傢傝丄懳抲偡傞傕偺偩偭偨偺偱偁傞丅懍搙姶偼丄帪戙傪傕偭偰戝偒偔曄傞傕偺偱偁傞丅攏幵偐傜尒傞晽宨偺棳傟傪儀乕僩乕償僃儞偼丄懍偄偲姶偠偨偩傠偆偑丄変乆偼偦傟傪抶偄偲偟偐姶偠側偄偩傠偆丅偟偐偟丄儀乕僩乕償僃儞偑丄妝晥偵儊僩儘僲乕儉婰崋傪揧偊偨弖娫丄偙偺儊僩儕僢僋偼丄姰慡側丄壢妛揑帪娫偵巟攝偝傟丄塱墦丄晄曄偺傕偺偲側傞丅偙傟偼悢抣偲偟偰偺帪娫奣擮偵懠側傜側偄丅堦曽偱丄偙偺傛偆偵丄儊僩儕僢僋側妝晥偵丄姶妎偱晄壜擻側偙偲傪婰弎偡傞偙偲偼丄乽峴堊偺巜帵乿偵傎偐側傜側偄丅墘憈壠偑丄妝晥傪奐偒丄儊僩儘僲乕儉婰崋傪尒偨傜丄斵偼傑偢丄儊僩儘僲乕儉傪庢傝埖傢側偗傟偽側傜側偄丅偙傟偼丄乽壒偺壜帇壔乿偲偄偆婰崋偱偼側偔丄乽峴堊偺巜帵乿偺婰崋壔偵傎偐側傜側偄丅
丂嶌嬋壠偲偄偆懚嵼偑尰傢傟偨嵟弶偺崰偼丄嶌嬋壠偼墘憈壠偦偺傕偺偱偁傝丄嶌嬋壠偼丄忢偵丄偁傞妝婍偺柤恖偲偟偰丄帺暘偑墘憈偡傞偨傔偵丄嶌嬋傪峴偭偨丅偝傜偵丄僆儁儔嵗偺壒妝娔撀傗媨掛偺帩偮僆乕働僗僩儔偺愱懏巜婗幰偺抧埵傪摼偰丄尵傢偽丄帺暘偺墘憈壠偨偪偺偨傔偵嶌嬋偼峴傢傟偰偄偨丅偦偺恖悢丄妝婍曇惉丄偦偟偰丄奺憈幰偺媄検偵丄偁傢偣偰偺嶌嬋偼偁偨傝傑偊偺偙偲偱偁偭偨丅偦偆偱偁傟偽丄嶌嬋壠偺媮傔傞壒妝偼丄傎偲傫偳偺応崌丄墘憈偵嵺偟偰丄帺暘偱峔惉偡傞偙偲偑弌棃偨丅偦偺曽朄偼丄婰弎偱偼側偔丄幚嵺偺墘憈傪夘偟偰揱偊傜傟傞屆戙偲摨偠曽朄偱偁偭偨傠偆丅偡側傢偪丄壒偼懱宯偵婎偯偄偰壜帇壔偝傟偨偑丄峴堊偺巜帵傪婰弎偡傞昁梫偼側偐偭偨偲偄偊傞丅屆戙偺壒妝偼丄懄嫽丄偡側傢偪丄晄妋掕側壒妝偱偁傝丄弌巒傔偺妝晥傕丄晄妋掕側傕偺偱偁偭偨丅屆戙偲摨偠壒妝峔惉偺曽朄偑偲傟傞偺側傜丄晄妋掕側傕偺偑偁偭偰傕峔傢側偄偺偱偁傞丅僥儞億傗僼儗乕僕儞僌 phrasing乵拲73乶 側偳偑丄婰偝傟偰偄側偄妝晥偼丄屆揟攈偺帪戙偺傕偺偱傕懚嵼偡傞丅偁傞偄偼丄捠憈掅壒偺婰晥朄偼丄敽憈偵晄妋掕惈傪梌偊偰偄傞偲傕尵偊傞丅妋掕惈偼偙偺応崌丄婰晥朄偺懱宯傪堄枴偡傞丅椺偊偽丄僱僂儅晥偵偍偄偰偼丄壒壙偼丄妋掕偝傟偰偄側偄丅側偤側傜丄壒壙傪妋掕偡傞婰晥朄偺懱宯偑懚嵼偟側偐偭偨偐傜偱偁傞丅儊僩儕僢僋側掕検婰晥朄偵偍偄偰丄壒崅傗壒壙偼丄妋掕偝傟偨偑丄幚偼丄晄妋掕側傕偺傕彮側偔偼側偄偺偱偁傞丅
丂妋掕揑偲偄偆梫慺偼丄儀乕僩乕償僃儞傪旂愗傝偵丄惣梞偺壒妝壠偵捛媦偝傟傞傛偆偵側傞丅僥儞億偩偗偱側偔丄旝柇側僼儗乕僕儞僌傗丄壒検偺巜帵偼敋敪揑偵憹偊傞偙偲偵側傞丅偦偟偰丄偦偺傛偆側妝晥偺慜偵丄墘憈壠偨偪偼丄廬懏偟丄揙掙揑偵丄妝晥傪帄忋偲偡傞墘憈棟擮傪嶌傝弌偟偰偄偔偺偱偁傞丅妋掕揑偐晄妋掕揑偐偱丄壒妝傪榑偠傞偙偲偑嫋偝傟傞偺側傜偽丄僗僩儔償傿儞僗僉乕偼丄妋掕揑壒妝偺嵟戝偺嶌嬋壠偱偁傞丅斵偵偲偭偰丄墘憈壠偲偼丄偨偩巜掕偝傟偨壒傪弌偣偽椙偄傕偺偱偁偭偰丄斵偺妝晥偼丄愨懳桞堦偺丄偮傑傝嶌嬋壠帺恎偺夝庍偵傛偭偰寴楽偵庣傜傟偰偄傞姶偑偁傞丅嶌嬋壠偺朷傓壒傪巜掕偡傞偨傔偵偼丄壜帇壔偱偒側偄乽峴堊偺巜帵乿偑丄昁梫偵側傞丅偦偟偰丄乽峴堊偺巜帵乿偺斆棓傪巭傔傞偙偲偼偱偒側偐偭偨丅
丂崱悽婭偺妋掕揑壒妝偵偍偄偰丄廬棃偺壒妝傪壜帇壔偡傞曽朄偼偝傎偳廳梫偱偼側偔側傞丅側偤側傜丄挳妎寍弍偱偁傞壒傪壜帇壔偡傞偲偄偆偙偲帺懱偑丄偡偱偵丄晄妋掕惈傪娷傫偱偟傑偆偐傜偱偁傞丅晄妋掕惈傪娷傫偩攠夘偑丄嶌嬋壠偲墘憈壠偲偄偆堎側傞恖暔偺娫偱偲傝岎偝傟傟偽丄偦偙偵偼丄昁偢丄曄幙偑婲偙傞丅偙偺曄幙傪寵偆側傜偽丄揹巕壒妝偺妝晥偺傛偆偵丄乽僷儔儊僩儕僢僋乿側妝晥傪峔抸偡傞昁梫偑偁傞丅儔偱偼側偔丄442僿儖僣偺壒傪丄巐暘壒晞偱偼側偔丄壗昩偺帩懕偲偄偆傛偆偵丄嶌嬋壠偼丄旝嵶側壒傪婯掕偱偒丄偝傜偵丄僷儔儊乕僞乕揑妝晥偼丄乽峴堊偺巜帵乿傪埑搢揑偵尭傜偡丅側偤側傜丄廬棃丄壜帇壔偱偒側偐偭偨偦傟傜偺峴堊偼悢抣壔偟丄僌儔僼壔偱偒傞偐傜偱偁傞丅僷儔儊乕僞乕揑妝晥偼丄乽峴堊偺巜帵乿傪乽壒偺壜帇壔乿偲偟偰昞傢偣傞婰晥朄偩偭偨丅乽p--mp--mf--f乿偺楢側傝偼丄寛偟偰壒偺憹壛傪壜帇壔偟偰偄傞傕偺偱偼側偐偭偨丅僋儗僢僔僃儞僪偺婰崋傕丄憹壛偺恾幃壔偵偡偓側偄丅偑丄慄偱偁傜傢偝傟偨僨僔儀儖偺僌儔僼偼偁偒傜偐偵壒偺慟憹傪壜帇壔偟偰偄傞丅偦偟偰丄嵞尰柺偱偦傟傪壜擻偵偡傞偺偑丄揹巕壒妝偱偁傞丅偟偐偟丄偦偺帪丄揹巕壒妝偺乽墘憈偝傟側偄乿偲偄偆惈幙傪朰傟偰偼偄偗側偄丅揹巕壒妝偺妝晥偼丄嶌嬈曬崘偲偟偰偩偝傟偨尋媶梡偺妝晥偲偟偰偺堦柺偑偁傞偐傜偱偁傞丅偮傑傝丄墘憈偵懳偡傞峴堊偺巜帵偼傕偲偐傜昁梫偑側偄偲傕尵偊傞偺偩乵拲74乶 丅
丂妋掕惈傪栚巜偡堦楢偺摦偒偲偼媡偵丄儘儅儞攈偺妝晥偵戙昞揑側僥儞億丒儖僶乕僩 Tempo rubato偼丄乽搻傑傟偨僥儞億乿傪堄枴偟丄僼儗乕僘偺怢傃弅傒傪墘憈壠偑帺桼偵慖戰偱偒傞丅偙傟偼丄庡偵丄僼儗僨儕僢僋丒僔儑僷儞 Fredeic Chopin (1810-1849) 偺妝晥偵尒偄弌偡偙偲偑偱偒丄偦傟偼丄嶌嬋壠偵傛偭偰丄墘憈偺僥儞億偑晄妋掕偱偁傞偙偲偑擣傔傜傟偨妝晥偲偄偆偙偲偵側傞丅僥儞億丒儖僶乕僩偼丄儘儅儞僥傿僔僘儉偺戙昞偲偟偰丄屻偺帪戙偵婖傒寵傢傟傞偑丄偦偺晄妋掕惈偼丄尰戙偺壒妝偺庡棳偵側傞丅嬼慠惈偺壒妝偲屇偽傟傞傕偺偼丄僕儑儞丒働乕僕 John Cage(1912-1992) 偵傛偭偰嵦梡偝傟偨丅偦偺曽朄榑偼偄偔偮偐偁傞丅椺偊偽丄嶌嬋偺抜奒偱丄嬼慠惈傪巊偆傕偺丄椺偊偽丄乻堈偺壒妝Music of Changes乼(1951) 丄墘憈壠偺懄嫽惈偵傛傞傕偺丄椺偊偽丄乻僺傾僲偲僆乕働僗僩儔偺偨傔偺墘憈夛Concert for piano and orchestra乼(1958)乮晥椺3-7乯 側偳偱偁傞丅偙偺乻僺傾僲偲僆乕働僗僩儔偺偨傔偺墘憈夛乼偱偼丄墘憈壠偨偪偼丄帺傜偺帺屓娗棟偺傕偲偱丄帺桼偵墘憈晹暘傪慖戰偟丄拋彉傗帩懕傕奺帺偺嵸検偵擟偝傟偰偄傞丅偙偺傛偆側丄墘憈偱偼丄拤幚側僗僐傾丒儕乕僟乕偲偟偰偺墘憈壠偱偼丄幐奿偲偄偆偙偲偵側傞丅偦傟偧傟偑丄嶌嬋幰偺椞堟傑偱丄奐戱偟偰峴偐側偗傟偽丄墘憈偼偱偒側偄丅嶌嬋幰偑梌偊傞偺偼丄妋掕偟偨壒妝偱偼側偔丄墘憈壠偺懄嫽揑憂憿椡偺婲敋嵻偲偟偰偺堄枴丄僐儞僙僾僩偱偁傞丅嶌嬋壠偲丄偦傟偵廬懏偡傞墘憈壠偱偼側偔丄椉幰偺奯崻偼庢傝暐傢傟傞丅偟偐偟丄壒妝偺嵞尰惈傪捛媦偟偨妝晥偺嵼傝曽偲偼丄堦慄傪夋偡傞丅傓偟傠丄妝晥傪偍偲偟傔傞偨傔偵岲傫偱巊傢傟偰偒偨乽妎偊彂偒乿偵奣擮偼旵揋偡傞丅廬棃偺墘憈偱偼側偔丄墘憈幰偵偼丄慖傫偩傝丄僎乕儉傪偟偨傝丄尞斦偵搳慘偟偨傝偲偄偆乽峴堊偺巜帵乿偑懡偔梌偊傜傟傞丅妝晥忋偵偼丄廬棃偺壒妝梡岅偱偼側偄悢懡偔偺暥帤偑彂偐傟偰偄傞丅偦傟偼丄嶌嬋壠帺恎偵傛傞挿戝側妝晥偺撉傒曽偐傜巒傑傞偺偑忢偩丅偙偺傛偆側僌儔僼傿僇儖側妝晥偼丄僨僓僀儞偲偟偰峫偊偨偄傛偆側傕偺傕偁傞乵拲75乶丅偙偺傛偆側壒妝傕丄偦偙偵側傫傜偐偺嵗昗偑懚嵼偡傞側傜丄偁傞堄枴乽僷儔儊僩儕僢僋乿側惈幙傪帩偭偰偄傞偲尵偊傛偆丅偟偐偟丄偙傟傜偺懡偔偼丄悇掕揑側妝晥偲尵傢偞傞傪摼側偄丅恾宍偑憡屳偵丄晄妋掕偩偑丄側傫傜偐偺検偲偟偰悇掕偱偒傞乽儊僩儕僢僋乿側娭學傪帩偭偰偄傞丅傓偟傠僱僂儅晥偺偁傝曽偵嬤偄慄昤揑側妝晥偱偁傞丅
側偳偱偁傞丅偙偺乻僺傾僲偲僆乕働僗僩儔偺偨傔偺墘憈夛乼偱偼丄墘憈壠偨偪偼丄帺傜偺帺屓娗棟偺傕偲偱丄帺桼偵墘憈晹暘傪慖戰偟丄拋彉傗帩懕傕奺帺偺嵸検偵擟偝傟偰偄傞丅偙偺傛偆側丄墘憈偱偼丄拤幚側僗僐傾丒儕乕僟乕偲偟偰偺墘憈壠偱偼丄幐奿偲偄偆偙偲偵側傞丅偦傟偧傟偑丄嶌嬋幰偺椞堟傑偱丄奐戱偟偰峴偐側偗傟偽丄墘憈偼偱偒側偄丅嶌嬋幰偑梌偊傞偺偼丄妋掕偟偨壒妝偱偼側偔丄墘憈壠偺懄嫽揑憂憿椡偺婲敋嵻偲偟偰偺堄枴丄僐儞僙僾僩偱偁傞丅嶌嬋壠偲丄偦傟偵廬懏偡傞墘憈壠偱偼側偔丄椉幰偺奯崻偼庢傝暐傢傟傞丅偟偐偟丄壒妝偺嵞尰惈傪捛媦偟偨妝晥偺嵼傝曽偲偼丄堦慄傪夋偡傞丅傓偟傠丄妝晥傪偍偲偟傔傞偨傔偵岲傫偱巊傢傟偰偒偨乽妎偊彂偒乿偵奣擮偼旵揋偡傞丅廬棃偺墘憈偱偼側偔丄墘憈幰偵偼丄慖傫偩傝丄僎乕儉傪偟偨傝丄尞斦偵搳慘偟偨傝偲偄偆乽峴堊偺巜帵乿偑懡偔梌偊傜傟傞丅妝晥忋偵偼丄廬棃偺壒妝梡岅偱偼側偄悢懡偔偺暥帤偑彂偐傟偰偄傞丅偦傟偼丄嶌嬋壠帺恎偵傛傞挿戝側妝晥偺撉傒曽偐傜巒傑傞偺偑忢偩丅偙偺傛偆側僌儔僼傿僇儖側妝晥偼丄僨僓僀儞偲偟偰峫偊偨偄傛偆側傕偺傕偁傞乵拲75乶丅偙偺傛偆側壒妝傕丄偦偙偵側傫傜偐偺嵗昗偑懚嵼偡傞側傜丄偁傞堄枴乽僷儔儊僩儕僢僋乿側惈幙傪帩偭偰偄傞偲尵偊傛偆丅偟偐偟丄偙傟傜偺懡偔偼丄悇掕揑側妝晥偲尵傢偞傞傪摼側偄丅恾宍偑憡屳偵丄晄妋掕偩偑丄側傫傜偐偺検偲偟偰悇掕偱偒傞乽儊僩儕僢僋乿側娭學傪帩偭偰偄傞丅傓偟傠僱僂儅晥偺偁傝曽偵嬤偄慄昤揑側妝晥偱偁傞丅 晥椺3-8偵偁偘偨僋僔僔僩僼丒儁儞僨儗僣僉 Krzysztof Penderecki (1933-)偺乻48偺尫妝婍偺偨傔偺億儕儌儖僼傿傾 Polymorphia乼偼丄偦偺嵟掅晹偵昩悢傪婰偟丄堦尒僷儔儊僩儕僢僋偵尒偊傞偑丄偙傟偼丄斾椺揑帩懕婯掕偲屇偽傟傞儊僩儕僢僋側曽朄榑偱偁傞丅昩悢偱嬫愗傜傟偨帪娫偺榞偼丄帇妎偑應傞濨枂側検偵傛偭偰墘憈壠偵墘憈偺宊婡偺帺屓敾掕傪擟偣傞偺偱偁傞丅晲枮揙 (1930-1998)偺乻尫妝偺偨傔偺僐儘僫厾乼(1962)乮晥椺3-9乯乵拲76乶 偺傛偆偵丄怓嵤偺擹扺側偳偑丄乽儊僩儕僢僋乿偵悇掕偝傟丄壒妝傪偮偔傝偩偡丅
晥椺3-8偵偁偘偨僋僔僔僩僼丒儁儞僨儗僣僉 Krzysztof Penderecki (1933-)偺乻48偺尫妝婍偺偨傔偺億儕儌儖僼傿傾 Polymorphia乼偼丄偦偺嵟掅晹偵昩悢傪婰偟丄堦尒僷儔儊僩儕僢僋偵尒偊傞偑丄偙傟偼丄斾椺揑帩懕婯掕偲屇偽傟傞儊僩儕僢僋側曽朄榑偱偁傞丅昩悢偱嬫愗傜傟偨帪娫偺榞偼丄帇妎偑應傞濨枂側検偵傛偭偰墘憈壠偵墘憈偺宊婡偺帺屓敾掕傪擟偣傞偺偱偁傞丅晲枮揙 (1930-1998)偺乻尫妝偺偨傔偺僐儘僫厾乼(1962)乮晥椺3-9乯乵拲76乶 偺傛偆偵丄怓嵤偺擹扺側偳偑丄乽儊僩儕僢僋乿偵悇掕偝傟丄壒妝傪偮偔傝偩偡丅
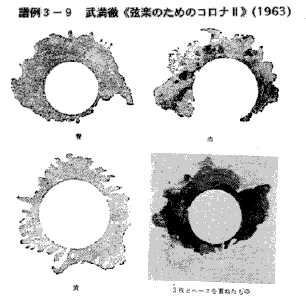 丂揹巕壒妝偺応崌傕丄嬼慠惈偺壒妝偺応崌傕丄尰戙偺怴偟偄壒妝偺岦偐偆愭偵偼丄嶌嬋壠偲偄偆懚嵼偺丄懠偲偺娭傢傝曽傪戝偒偔備傞偑偦偆偲偡傞孹岦偑尒偊傞丅嶌嬋壠偑帺暘埲奜偺懚嵼偵懳偟偰丄帵偡攠夘偱偁傞婰晥朄偵尰傢傟傞偙偺戝偒側曄堎偑偦傟傪暔岅偭偰偄傞偺偱偼側偐傠偆偐丅恾宍妝晥偼丄昐恖昐條偺妝晥偲宍梕偝傟傞丅偙偺僔僗僥儉偱偼丄婰晥朄傪嶌傞傕偺偑嶌嬋壠偱偁傝丄挳妎偵撏偔嬶懱揑側壒妝偼丄墘憈壠傗揹巕壒嬁偵傛偭偰乽嶌傜傟偰偄傞乿偲偄偭偰傕夁尵偱偼側偄丅僌儔僼傿僢僋側妝晥偵傛傞嬼慠惈偺壒妝偱偼丄僐儞億乕僓乕偲偄偆尵梩偑丄崱傗丄嶌嬋壠偲墘憈壠偺偳偪傜偵抲偐傟偰偄傞偺偐丄晄柧椖偵傕巚偊傞丅嶌嬋壠偼丄僲乕僥乕僞乕偲偟偰丄帺暘偺壒妝傪丄婰晥朄傪嬱巊偟偰壜帇壔偟傛偆偲偟偰偒偨丅偟偐偟丄廬棃偺婰晥朄偑丄偦偺壒妝傪漼旾偟偨寢壥丄妝晥偼丄僷儔儊乕僞乕偲偟偰悢抣壔偝傟偨傝丄峴堊偺巜帵偲偟偰僐儅儞僪壔偝傟偰偒偨丅傕偼傗丄婰晥朄偲挿傜偔屇偽傟偰偒偨丄戝偒側懱宯偵偝偊丄嬫愗傝偑懪偨傟傛偆偲偟偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄働儖儞偺僼儔儞僐偑帵偟偨僲乕僥乕僞乕偲偄偆奣擮偼丄偦傟偱傕丄婰晥偟偨傕偺偑嶌嬋壠偱偁傞偙偲傪丄俈悽婭偵傕搉偭偰惣梞偺昗弨偲偟偰偒偨乵拲77乶丅
丂揹巕壒妝偺応崌傕丄嬼慠惈偺壒妝偺応崌傕丄尰戙偺怴偟偄壒妝偺岦偐偆愭偵偼丄嶌嬋壠偲偄偆懚嵼偺丄懠偲偺娭傢傝曽傪戝偒偔備傞偑偦偆偲偡傞孹岦偑尒偊傞丅嶌嬋壠偑帺暘埲奜偺懚嵼偵懳偟偰丄帵偡攠夘偱偁傞婰晥朄偵尰傢傟傞偙偺戝偒側曄堎偑偦傟傪暔岅偭偰偄傞偺偱偼側偐傠偆偐丅恾宍妝晥偼丄昐恖昐條偺妝晥偲宍梕偝傟傞丅偙偺僔僗僥儉偱偼丄婰晥朄傪嶌傞傕偺偑嶌嬋壠偱偁傝丄挳妎偵撏偔嬶懱揑側壒妝偼丄墘憈壠傗揹巕壒嬁偵傛偭偰乽嶌傜傟偰偄傞乿偲偄偭偰傕夁尵偱偼側偄丅僌儔僼傿僢僋側妝晥偵傛傞嬼慠惈偺壒妝偱偼丄僐儞億乕僓乕偲偄偆尵梩偑丄崱傗丄嶌嬋壠偲墘憈壠偺偳偪傜偵抲偐傟偰偄傞偺偐丄晄柧椖偵傕巚偊傞丅嶌嬋壠偼丄僲乕僥乕僞乕偲偟偰丄帺暘偺壒妝傪丄婰晥朄傪嬱巊偟偰壜帇壔偟傛偆偲偟偰偒偨丅偟偐偟丄廬棃偺婰晥朄偑丄偦偺壒妝傪漼旾偟偨寢壥丄妝晥偼丄僷儔儊乕僞乕偲偟偰悢抣壔偝傟偨傝丄峴堊偺巜帵偲偟偰僐儅儞僪壔偝傟偰偒偨丅傕偼傗丄婰晥朄偲挿傜偔屇偽傟偰偒偨丄戝偒側懱宯偵偝偊丄嬫愗傝偑懪偨傟傛偆偲偟偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄働儖儞偺僼儔儞僐偑帵偟偨僲乕僥乕僞乕偲偄偆奣擮偼丄偦傟偱傕丄婰晥偟偨傕偺偑嶌嬋壠偱偁傞偙偲傪丄俈悽婭偵傕搉偭偰惣梞偺昗弨偲偟偰偒偨乵拲77乶丅
丂婰晥朄偼丄偦偺帪戙偺壒妝條幃偵傑偭偨偔懄偟偨宍偱惗傑傟傞偙偲偑丄偙偙傑偱偺愢柧偱丄柧敀偵側偭偨丅偟偐偟丄堦偮偺婰晥朄偑妋掕偟偨傕偺偵側偭偨偐傜偲偄偭偰丄壒妝偺楌巎偑偦偙偱巭傑傞傢偗偱偼側偄丅廬棃偺峘偵掆攽偡傞偙偲偑擄偟偄庬椶傗戝偒偝偺慏偼傑傕側偔嶌傜傟傞偙偲偵側傞丅偦偟偰丄偨偭偨崱丄尒偰偒偨傛偆偵丄尰戙偺嶌嬋壠偨偪傕條乆側堄恾偲曽朄傪帩偭偰怴偟偄婰晥朄傪奐戱偟偨丅偙偺恾宍妝晥偑丄尰戙偺壒妝條幃偺峴偒拝偄偨尰戙偺婰晥朄偩偲偡傞側傜偽丄僔儏僩僢僋僴僂僛儞偺偄偆傛偆偵丄嬤戙屲慄晥朄傕傗偑偰偼丄曄壔偡傞偩傠偆丅
丂嬼慠惈偺壒妝偑丄僶儘僢僋帪戙偺墘憈奣擮偵夞婣偟偰偄傞偲偄偆妛幰傕偄傞偑丄恾宍妝晥偺僱僂儅揑側夞婣偵偮偄偰丄僺僄乕儖丒僽乕儗乕僘偼丄乽侾丏掕検揑婰崋懱宯傪梡偄偰偄側偄丅俀丏偦傟偼偁傑傝慇嵶偱偼側偄丄偮傑傝戝嶨攃側嬤帡抣傪惗傒弌偡傛偆側恄宱峔憿傪傛傝偳偙傠偲偡傞丅俁丏偦傟偼丄壒妝揑側帪娫偺姰慡側掕媊傪柧傜偐偵偟側偄乿乵拲78乶偲偄偆嶰偮偺棟桼偐傜丄偦傟傪戅峴偲傒側偡丅枹棃偺婰晥朄偼丄偦傟偵愭峴偡傞傕偺傪曪妵偱偒傞偲偡傞側傜偽丄妋偐偵丄恾宍揑側妝晥偼丄廬棃偺婰崋偵傛傞婰晥朄傪柧傜偐偵偟側偄偲偄偆堄枴偱戅峴偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄偦偙偵丄壒偑壜帇壔偟偰偄側偄偲偼丄尵偊側偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅妝晥偼丄尩枾偵尵偊偽丄壒偺壜帇壔偱偼側偄丅偟偐偟丄壒傪壜帇壔偟偨傕偺偼丄側傫偲挿偄娫丄妝晥偲屇偽傟懕偗偰偒偨偙偲偩傠偆丅妋偐偵丄栚偵尒偊傞宍偵偟偰丄偦偺傕偺偐傜丄壜帇壔偟偨杮懱傪暘偐傞傛偆偵偡傞丄偲偟偨嵟弶偺掕媊偵徠傜偟崌傢偣傟偽丄恾宍妝晥偼丄戅峴偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄偦傟偼丄嵞尰惈偵廳揰傪偍偗偽偙偦偱偁傞丅偦偟偰丄偦偺寢壥丄憹壛偟偨偺偼丄弮悎側乽壒偺壜帇壔乿偱偼側偔乽峴堊偺巜帵乿偱偁傝丄乽儊僩儕僢僋乿偺乽僷儔儊僩儕僢僋乿傊偺堏峴偱偁傞丅偟偐偟丄婰晥朄偺條幃偐傜丄壒妝偺惀旕傪寛傔傞偙偲傕傑偨偱偒側偄偺偱偁傞丅婰晥朄偑偁偭偰壒妝偑偁傞偺偱偼側偄偺偩偐傜丅偟偐偟丄挿偄婰晥朄偺楌巎傪専摙偟偰偒偰丄偙偆偼尵偊傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅懡條壔偡傞尰戙偺儊僨傿傾偺拞偱丄妝晥偲偄偆堦偮偺儊僨傿傾偑丄壒妝偺惂嶌丄嵞尰丄婰榐丄揱攄丄曐懚偺慡偰傪廤栺揑偵壥偨偝側偗傟偽側傜側偄昁慠惈傕傑偨側偄偺偱偼側偐傠偆偐丅嵟弶偵帵偟偨乽婯斖揑乿側妝晥偲乽婰弎揑乿側妝晥偺擇暘朄偵徠傜偟偰尵偊偽丄偡偱偵丄乽婯斖揑乿側妝晥偲偟偰丄嬤戙屲慄晥朄偵傛傜側偄嶌嬋偲墘憈偼側偝傟偰偄傞丅偦偟偰丄偦傟傪乽婰弎揑乿偵婰榐偟曐懚偡傞儊僨傿傾傕変乆偼妉摼偟偰偄傞偼偢偱偁傞丅妝晥傪乽妎偊彂偒乿偱偼側偄偲偟丄婰榐丄揱攄丄曐懚丄嶌嬋偲偦偺愽嵼惈傪旘桇揑偵崅傔偨帠偱丄惣梞偺壒妝偼丄懠偵椶傪尒側偄揥奐傪偲偘偨丅偟偐偟丄偦偆偄偭偨傕偺偑丄帪戙揑偵丄偁傞偄偼丄嬻娫揑偵丄偨傑偨傑丄惛枾側嵞尰惈傪梫媮偝傟丄曐帩偟偰偄偨偩偗側偺偐傕偟傟側偄丅偦偆峫偊傟偽丄恾宍妝晥偵懳偡傞傢傟傢傟偺帇慄傕偍偩傗偐側傕偺偵側傞偩傠偆丅媡偵丄敊慠偲壒偺椫妔傪悇掕偡傞偲偄偆忬懺傪杮棃偺壜帇壔偩偲偄偆偺側傜丄掕検婰晥朄偐傜嬤戙屲慄晥朄偵偄偨傞婰晥朄偼丄幚偼丄壜帇揑婰崋傪傕偲偵應掕偝傟傞嵗昗偲傕偄偊傞丅妝晥偺堄媊傪婯掕偡傞帪偺梫慺偼丄妝晥偺杮幙揑側懺搙偲偼娭學側偔丄恖乆偑妝晥偵媮傔偰偒偨壜擻惈偺徾挜側偺偐傕偟傟側偄丅偦偺堄枴偱偼丄媮傔傜傟傞儊僨傿傾惈傪曻婞丄偁傞偄偼惂尷偟偨偙偲偑尰戙偺恾宍妝晥偺壥偨偟偨峷專偲尵偊傞偩傠偆丅儊僨傿傾傪慖戰偡傞偙偲偱丄壒偺壜帇壔偝偊傕偑堘偆堄枴傪帩偭偰棃傞偺偱偁傞丅寢榑傪徟傞昁梫傕傑偨側偄偑丄恾宍妝晥傪丄楢柸偲懕偄偰偒偨壒妝偺壜帇壔偺楌巎偺丄堦偮偺僆儖僞僫僥傿償偲峫偊傞偙偲偼偱偒傞偩傠偆乵拲79乶丅墘憈廳帇偺嬼慠惈偺壒妝偩偗偵尷傜偢丄幚嵺丄妝晥偑乽嶌昳乿傪峔惉偡傞偲偄偆帪戙傕夁嫀偺傕偺偵側傝偆傞偺偱偁傞丅偦傫側拞偱丄壒妝偺壜帇乮昞尰乯壔偼丄儈僋僗僩丒儊僨傿傾丄儅儖僠丒儊僨傿傾偺柤偺尦偵丄偁傜備傞寍弍壠偺庤偱丄峴傢傟偰偄傞丅偙傟偐傜偼丄妝晥偲偄偆尵梩偱丄壒妝偺壜帇壔傪偳偙傑偱尵偄昞偡偙偲偵側傞偺偱偁傠偆偐丅彉榑偱戅偗偨傛偆側丄壒妝偺壜帇昞尰傕丄壒偺壜帇壔偲偟偰妝晥偲屇傃偆傞儊僨傿傾惈傪擣傔傞帪戙傕棃傞偺偩傠偆丅偁傞嶌嬋壠偑丄偙傟偼妝晥偩偲偄偭偰梮傝弌偟偨帪丄巹偨偪偼丄偦傟傪徫偆偙偲偑偱偒傞偩傠偆偐乵拲80乶丅 寢榑偼偁偒傜偐偱偁傞丅婰晥朄偺曄壔偼丄壒妝偺曄壔偲傑偭偨偔愗傝棧偣側偄娭學偵偁傞丅偦偟偰丄壒妝偺條幃偑丄傛傝壜帇揑側昞尰宍懺傪栚巜偡尰戙偺壒妝偵偍偄偰丄妝晥偲偼偳偺傛偆側堄媊傪帩偪偆傞偺偱偁傠偆偐丅尰戙偺妝晥偑夁嫀偺妝晥傛傝桪傟偰偄傞偲偄偆偙偲偼側偄偲嵟弶偵弎傋偨丅側傜偽丄偦傟傜偼丄曎暿揑偵丄昡壙偝傟傞傋偒偱偁傞丅偄傑傗丄惣梞壒妝偼丄妋幚偵悽奅傪姫偒崬傒敪揥偟偰偄傞丅150擭偺僗僷儞偱偺梊應偑偙偺傑傑懕偔偺偩偲偡傟偽丄壒妝偺師偺帪戙偼丄2050擭偐傜巒傑傞偙偲偵側傞丅崱屻偺妝晥偼丄尰戙揑側儊僨傿傾偲愗傝棧偟偰峫偊傞偙偲偼偱偒側偄偩傠偆丅師乆搊応偡傞怴偟偄妝晥傪婃柪偵嫅傓偺側傜丄偦傟偼丄儌乕僣傽儖僩偺嬋傪傾儖僗丒僲償傽偺婰晥朄偵堏晥偡傞偙偲傪庡挘偡傞偺偲摨偠偙偲偵側傝偐偹側偄丅偦傟偼丄偦偺壒偺壜帇壔偵丄妝晥偲尵偆柤偑偮偗傜傟傞尷傝曄傜側偄恀棟側偺偱偁傞丅(椆)
嶲峫暥專仌偁偲偑偒傊